技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
最新GMPおよび関連ICHガイドライン対応実務
最新GMPおよび関連ICHガイドライン対応実務
- 医薬品
- Annex1
- CAPA (Corrective Action and Preventive Action / 是正措置・予防措置)
- CQA (Critical Quality Attributes / 重要品質特性)
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- GQP (Good Quality Practice)
- ICH Q11
- ICH Q12
- ICH Q13
- ICH Q3
- ICH Q3C
- ICH Q3D
- ICH Q3E
- ICH Q8
- ICH Q9
- LIMS (ラボラトリー情報管理システム / Laboratory Information Management System)
- PQR (Product Quality Review / 製品品質照査)
- PQS (Pharmaceutical Quality System / 医薬品品質システム)
- クリーンルーム
- コンピュータ化システムバリデーション (CSV)
- 微生物試験
- 水処理
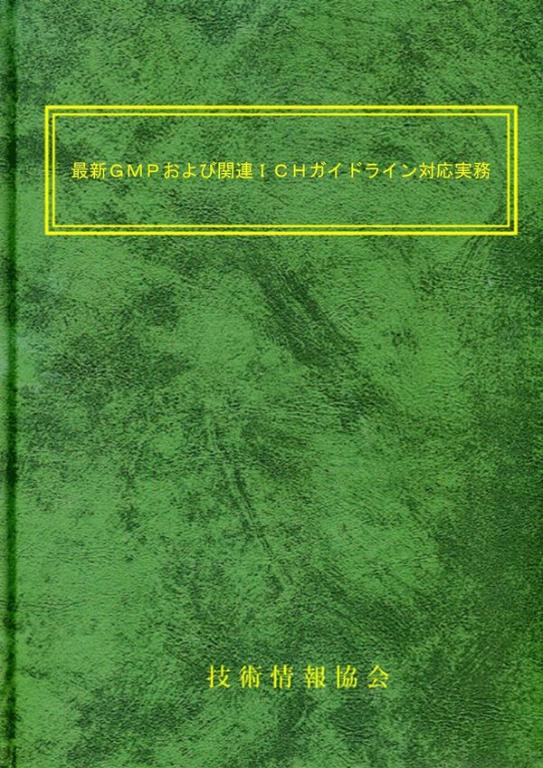
ご案内
- 【1】 品質システム (PQS) 構築の要件と具体的対応法
- 品質リスクマネジメント (QRM) の具体的進め方
- 変更マネジメントとQ12「ライフサイクルマネジメント」
- 製造業者として申請書記載内容のグレー部分への対応
- 製造業者としての異常/逸脱の現場判断と対応の効率化
- 医薬品品質システムにおける責任役員の役割とマネジメントレビュー
- 【2】 GMP文書と作成・管理
- 改正GMP省令で作成/改訂が求められるGMP文書とその作成
- 不正、逸脱を回避する手順書・記録書の作成・管理のポイント
- 【3】 PQSに対応した品質保証・監査
- 改正GMPに対応したQA (品質保証) 部門構築
- PQS実効性の監査
- 外国製造所や原料サプライヤーの管理
- 製造販売業者としての承認書コンプライアンス
- 【4】 データインテグリティ (DI) への対応
- 製造部門で注意すべきDI対応のポイント
- 試験検査室で注意すべきDI対応のポイント
- DIに対応した生データの取り方・管理のポイント
- データインテグリティに関する従業員の教育訓練
- 【5】 交叉汚染の防止
- 改正GMP省令における交叉汚染防止の要件
- 交叉汚染防止のための許容値 (PDE/AI) 設定・毒性評価法
- 改正GMPをふまえた洗浄バリデーションと設備共用の可否判断
- PIC/S GMP Annex1に寄与する無菌医薬品の微生物試験とそのバリデーション
- 製薬用水管理に関する規制動向とGMP管理項目
- 空調設備に求める交叉汚染防止要件
- 【6】 不純物規制と求められる管理戦略
- ICH Q (Q3C、Q3D) 対応の要点
- ICH M7 (変異原性不純物) で求められる不純物管理
- 原薬中、製剤中のそれぞれでのニトロソアミン類の管理
- 元素不純物の試験法設定及びバリデーションの事例
- ニトロソアミン類混入を防ぐ原料資材メーカーの選定・監査
- 【7】 医薬品工場のDX推進とGMP・DIへの対応
- 医薬品工場におけるIoT活用・生産の自動化とDI対応
- DX推進に伴う生産データの取得・蓄積と最大活用
- 製薬業界におけるデジタルツインと工場の最適化
- DXによる品質保証の効率化への取り組み
- 【8】 連続生産の管理戦略・GMP対応と実装事例
- ICH Q13の概要と原薬の連続生産プロセスの開発/管理戦略
- 固形製剤における連続生産プロセスの管理戦略
- 造粒乾燥工程から打錠工程までの連続化の取り組み事例
- バイオ医薬品における連続生産プロセスの構築と品質管理
- 連続ロセス構築への機械学習の活用~フロー合成の事例
目次
第1章 品質システム (PQS) 構築の要件と具体的対応法
1節 改正GMP省令における品質システム (PQS) 構築の要件
- 1.GMP省令改正
- 1.1 日本のPIC/S加盟
- 1.2 GMP省令改正 (経緯と概要)
- 2.改正GMP省令の主旨
- 3.改正GMP省令の条文構成
- 4.改正GMP省令のポイント
- 5.医薬品品質システムの概念
- 6.改正GMP省令で規定される医薬品品質システム
- 6.1 医薬品品質システムの構築と運用
- 6.2 医薬品品質システムの構築のために
- 6.2.1 品質マニュアル
- 6.2.2 品質マネジメントレビュー手順書
- 6.2.3 品質リスクマネジメントの基本的な考え方
- 6.2.4 品質リスクマネジメント手順書
- 7.GMP事例集 (2022) における医薬品品質システム
2節 品質リスクマネジメント (QRM) の具体的進め方
- 1.ICHQ9の品質リスクマネジメント
- 2.2022年GMP事例集の品質リスクマネジメント
- 3.「過去問」対策がリスク回避の近道
- 4.製造現場での不正をなくす方法
- 5.経営トップが招くリスク
- 6.「心理的安全性」の確保
- 7.自分たちのレベルの検証
- 7.1 普段ないピークの報告
- 7.2 過量仕込みの視点から
- 7.3 分析バリデーションの視点から
- 7.4 OOS処理の妥当性
- 7.5 習慣性医薬品の保管
- 7.6 データの見方
- 7.7 化血研の一斉点検の対応
- 7.8 溶出試験の高い値
- 7.9 塩酸リルマザホンとリルマザホン塩酸塩の名称違い
- 7.10 文書で逸脱報告を出すことの意味
- 8.一人ひとりの思いと行動
3節 変更マネジメントとQ12「ライフサイクルマネジメント」の実践
- 1.はじめに
- 1.1 CMC に関連する物性評価の項目
- 1.2 新薬開発と新薬申請
- 2.ICH Q12ガイドラインと関連するICH 品質ガイドライン
- 3.PLCM について (ICH Q12)
- 3.1 製品戦略を左右する製品ライフサイクルの 4つの段階
- 3.2 PLCM の限界 (ICH Q12)
- 4.CMC承認後変更のマネジメント (ICH Q8 (R2) 及び Q11 ガイドライン)
- 4.1 PLCMと製造の変更管理
- 4.2 ICH Q8 (R2) 製剤開発 10)
- 4.3 Q10 医薬品品質システム 11,12)
- 4.4 Q11 原薬の開発と製造 13)
- 4.5 PLCMと固体物性技術 13)
- 4.6 塩形・結晶形の特許
- 4.7 結晶特許の具体例
- 5 医薬品の PLCM の事例
- 5.1 抗潰瘍治療剤ザンタックの製品ライフサイクル
- 5.2 医薬品ライフタイムマネージメント
- 5.3 PLCM と製剤技術
- 5.4 PLCMによる市場の拡大と製品価値の最大化19)
- 6.まとめ:経営陣の責任 27)
- 6.1 経営陣のコミットメント
- 6.2 品質方針
- 6.3 製品所有権における変更の管理
4節 品質リスクマネジメントを取り入れた製剤開発の事例
- 1.Q9の改正について
- 1.1 主な改正内容
- 1.2 ハザード特定
- 1.3 品質リスクマネジメントの方法論
- 1.4 品質リスクマネジメントの形式性
- 1.5 リスクベースの意思決定
- 1.6 主観性の管理と最小化
- 1.7 製品の安定供給リスクに対応する上での品質リスクマネジメントの役割
- 2.品質リスクマネジメントを取り入れた製剤開発の基本的考え方
- 3.品質リスクマネジメントを取り入れた製剤開発の事例
- 3.1 開発の一環としての品質リスクマネジメント
- 3.2 パイロットスケール段階での品質リスクマネジメント
- 3.3 重要品質特性
- 3.4 重要工程・重要パラメータの推定と重要品質特性の管理戦略の提案
- 3.5 重要工程及び重要中間体の管理
5節 QbDを用いた造粒プロセスの設計事例と変更管理への活用
- 1.QbDによる製剤開発
- 1.1 従来の製剤開発とQbDによる製剤開発との比較
- 1.2 QbDに基づく製剤開発
- 2.ICH Q8による造粒工程の設計
- 2.1 撹拌造粒により粒度分布がシャープで収率の良い顆粒を得るための条件
- 2.2 撹拌造粒により高細粒収率を得るための最適化とデザインスペース
- 2.3 流動層造粒で目的粒径を得るためのCPP (重要工程パラメータ) を特定
- 3.QbDを用いた造粒プロセスの設計事例10)
- 3.1 処方および目標製品品質プロファイル (QTPP)
- 3.2 乾式造粒における要因と工程パラメータ
- 3.3実験計画法
- 3.4乾式造粒実験方法
- 3.5 顆粒の製品品質・CQAに対する寄与度および設計の最適化
- 3.6 顆粒の設計・生産およびデザインスペース
- 4.QbD変更管理への活用
6節 製造業者として申請書記載内容のグレー部分への対応
- 1.日米欧における変更事項の重度区分
- 2.軽微変更/一部変更申請の確認
- 3.一部変更承認 (一変) 申請の判断と記載法
- 3.1 品質に影響するかどうかの判断
- 3.2 各社によって判断が分かれていると思われている点;
- 4.MF登録事項の変更
- 5.薬事対応 (一変/軽微) の判断
- 5.1 軽微変更か、一変申請が必要な変更かは第0210001号通知に基づいて判断
- 5.2 製造販売承認書の記載からの判断
- 5.3 製造販売承認書の記載 (届出事項と一変事項) と当局の判断の相違の場合
7節 医薬品品質システムを活用した製造販売承認事項の遵守体制構築
- 1.改正GMP省令における承認事項の遵守
- 2.承認事項と製造方法の相違が生じる要因
- 3.変更管理における製造業者と製造販売業者 (MFにおける国内管理人) のコミュニケーション
- 4.品質システムの活用
- 5.知識管理における課題
8節 製造業者としての異常/逸脱の現場判断と対応の効率化
- 1.逸脱管理とは
- 2.逸脱の範囲
- 3.逸脱処理手順 (逸脱の管理)
- 3.1 逸脱の是正・予防措置 (CAPA) の目的
- 3.2 逸脱の区分管理とリスクマネジメント4)
- 3.3 試験規格逸脱 (OOS) 対応
- 3.4 CAPA対応のおける留意点
- 4.逸脱防止のための教育訓練
- 5.その他、逸脱の一般的な事例
9節 社内のクオリティーカルチャーの醸成
- 1.なぜクオリティカルチャーが重要視されることになったか
- 2.不正が生まれるメカニズム
- 3.不正文化は静かに進行し、容易に取り除けない
- 4.些細な事をおろそかにしない
- 5.割れ窓理論に学ぶ
- 6.心理的安全性を高める
- 7.トップの意識が重要
10節 試験検査室における教育訓練
- 1.試験検査室の役割と責任
- 1.1 品質管理の重要性
- 1.2 倫理とコンプライアンス
- 2.人材育成と教育プログラム
- 2.1 企業の品質方針と教育プログラムとの関連付け
- 2.2 試験検査室の教育の進め方
- 3.実効性のある教育訓練のために
- 3.1 OJT (On the JOB Training) 重視のトレーニング
- 3.2 技能評価試験の実施
- 3.3 試験メンター制度の導入
- 3.4 継続的な学習環境の提供
- 3.5 ピアレビュー制度
- 3.6 モチベーション向上策の検討
- 3.7 最新技術の導入
- 4.不正防止のための教育
- 4.1 不正の三要素
- 4.2 試験検査室で起こりうる不正
- 4.3 不正防止策の整備
- 4.4 不正防止策の教育
11節 製品品質照査による品質リスクマネジメント
- 1.「製品品質照査」導入の経緯とその背景
- 1.1 改正GMP省令における規定 (施行通知から省令へ)
- 1.2 「製品品質照査」の目的
- 1.3 照査すべき項目
- 1.4 製品品質照査実施の基本的な考え方
- 1.5 製品品質の照査報告書記載例
- 1.6 製品品質照査の手順書
- 2.品質リスクマネジメント
- 2.1 品質リスクマネジメントとは
- 2.2 品質リスクマネジメントの基本的な考え方
- 3.本ガイドラインの改正の要点
- 4.製品品質照査における品質リスクマネジメント
- 4.1 製品品質照査における品質リスクマネジメントの考え方
- 4.2 具体的な品質リスクマネジメントの実施方法
- 4.3 GMP事例集 (2022) における品質リスクマネジメントの考え方
- 4.4 品質リスクマネジメントに関するガイドラインの付属書II
12節 医薬品品質システムにおける責任役員の役割とマネジメントレビュー
- 1.品質システムの構築
- 1.1 GMP省令第3条の3
- 1.2 施行通知
- 1.3 GMP事例集
- 2.マネジメントレビュー
- 3.製造業者経営陣の役割
第2章 改正GMPに対応したGMP文書と作成・管理
1節 改正GMP省令で作成/改訂が求められるGMP文書とその作成
- 1.GMP文書
- 1.1 GMP省令第20条
- 1.2 施行通知
- 1.3 GMP事例集
- 2.手順書
- 2.1 GMP省令第8条
- 2.2 施行通知
- 2.3 GMP事例集
- 3.手順書
- 3.1 GMP省令文書及び記録の完全性の確保
- 3.2 ALCOA+
- 3.3 Attributable (帰属)
- 3.4 Contemporaneous (同時的)
- 3.5 Complete (完全であること)
- 3.6 不十分だった事例
- 4.GMPの基本
2節 不正、逸脱を回避する手順書・記録書の作成・管理のポイント
- 1.不正・逸脱はなぜ起こるか‐ヒューマンエラーとエラーマネジメント
- 2.GMPが求める文書作成のポイント‐Master Plan、SOP、MBR-
- 3.医薬品製造現場における教育訓練とその効果
- 4.査察に見る製造現場の文書管理
- 5.医薬品品質システムとQuality Culture
第3章 改正GMP・PQSに対応した医薬品の品質保証・監査
1節 改正GMPに対応したQA (品質保証) 部門構築
- 1.海外のガイドラインに見る品質部門の業務
- 1.1 PICS GMPに見る品質管理と品質保証業務について
- 1.2 FDA CFR211に見る品質管理と品質保証
- 2.GMP省令に見る品質保証と品質管理
- 2.1 品質部門の組織
- 2.2 製造管理者 (5条)
- 2.3 品質部門
2節 PQS実効性での監査の着眼点
- 1.改正GMP省令の要点と改正事項
- 2.各改正事項に対する監査の着眼点と対応のポイント
- 2.1 医薬品品質システム関連 (第3条の3)
- 2.2 品質リスクマネジメント (第3条の4)
- 2.3 製造部門及び品質部門 (第4条)
- 2.4 手順書等 (第8条)
- 2.5 交叉汚染の防止のための手順 (第8条の2)
- 2.6 構造設備の共用等の管理の明確化 (第9条)
- 2.7 参考品、保存品管理、OOS規定の省令化 (第11条1項)
- 2.8 安定性モニタリングの規定 (第11条の2)
- 2.9 年次製品品質照査 (11条の3)
- 2.10 原料等の供給者管理 (11条の4)
- 2.11 外部委託業者の管理 (第11条の5)
- 2.12 変更マネジメント概念の導入 (第14条)
- 2.13 逸脱処理の強化 (第15条)
3節 外国製造所の監査での留意点
- 1.監査の計画
- 1.1 監査のタイプ
- 1.2 監査頻度
- 2.監査の準備
- 2.1 監査日程の交渉
- 2.2 監査チームの編成
- 2.3 海外渡航に関する準備
- 2.4 通訳の手配
- 2.5 事前資料の要求
- 2.6 リスクの抽出、分析、絞り込み
- 2.7 監査アジェンダ (Audit Agenda) の作成・送付
- 3.監査の実施
- 3.1 開始ミーティング (Opening meeting)
- 3.2 現場ツアー (Site tour)
- 3.3 書類確認 (Document Review)
- 3.4 監査のまとめ (Auditor meeting)
- 3.5 講評 (Closing meeting)
- 4.監査レポートとフォローアップ
- 4.1 監査レポートの作成・送付
- 4.2 是正予防措置 (CAPA) の提出・確認
- 4.3 監査の最終評価とフォローアップ
4節 原料等の供給者の管理と監査
- 1.供給者管理に関する規制・ガイドライン
- 1.1 規制・ガイドラインの種類
- 1.2 代表的規制・ガイドラインの各条
- 2.原料等のカテゴリーと管理を要求される項目
- 2.1 製剤・原薬
- 2.2 出発原料以降の場合
- 2.3 出発原料の場合
- 2.4 出発原料以前の場合
- 2.5 一次医薬品包装容器 (Primary Packaging Material) 及びその材料
- 2.6 医薬品と接触する資材、機器
- 2.7 医薬品添加物
- 3.供給者の管理
- 3.1 管理の仕組み
- 3.2 管理の実際
5節 「GMP監査マニュアル」の活用のポイント
- 1.本マニュアルについて
- 1.1 本マニュアルを活用する際の注意点
- 1.2 本マニュアルの構成
- 2.GMP監査とは
- 2.1 目的
- 2.2 GMP監査の本質
- 3.GMP監査体制
- 3.1 組織
- 3.2 教育訓練
- 3.3 認定と更新
- 4.サブシステムを踏まえた監査
- 5.GMP監査体系
- 5.1 監査区分
- 5.2 選定調査
- 5.3 初回監査
- 5.4 定期監査
- 5.5 監査手法
- 5.6 監査日数
- 6.監査計画
- 6.1 定期監査の頻度
- 6.2 製造所の業務リスク
- 6.3 定期監査の頻度例
- 6.4 監査年間計画書
- 6.5 監査手法の選択
- 6.6 チームリーダーの指名
- 7.実地監査
- 7.1 監査の準備
- 7.2 監査の実施
- 7.3 ラップアップミーティング
- 7.4 指摘事項の説明での注意点
- 7.5 改善要請事項と要望対応事項
- 8.監査実施状況等のレビュー
- 8.1 監査後のレビュー
- 8.2 監査実施状況のレビュー
6節 製造販売業者としての承認書コンプライアンス
- 1.昨今の法令・承認書コンプライアンス違反
- 1.1 法令・承認書コンプライアンスに関する業界の現況
- 1.2 法令・承認書コンプライアンスに関する通知
- 2.法令の改正とその対応
- 2.1 薬機法の改正
- 2.2 GMP省令の改正
- 3.グローバル化への対応3)
- 3.1 グローバル化における承認書コンプライアンスにおける課題
- 3.1.1 海外製造所の日本の薬事要件に対する理解不足
- 3.1.2 製造所管理の複雑化・広域化
- 3.2 グローバル化における承認書コンプライアンス対応
- 3.2.1 日本の薬事要件に関するトレーニングの実施
- 3.2.2 標準化を目的としたグローバル手順の導入
- 3.2.3 継続的な海外製造所とのコミュニケーション
- 3.1 グローバル化における承認書コンプライアンスにおける課題
7節 GQPの観点からの品質問題の再発防止の対策
- 1.GQP実施上の問題点
- 2.製造販売業者と製造業者が適切な委受託を行うためのポイント
- 2.1 製造委託先の選定時のポイント
- 2.2 製造委託先との取決め時のポイント
- 2.3 製造委託先との取決め後のポイント
- 2.4 製造販売業者の品質管理の体制の整備
第4章 データインテグリティ (DI) への対応
1節 GMP管理におけるデータの電子化とDI対策
- 1.GMP現場における電子化傾向
- 1.1 業務プロエスにおける電子化のメリット
- 1.2 品質試験領域での電子化
- 1.3 製造領域での電子化
- 1.4 ハイブリッド対応の現状と課題
- 2.電子化に対する規制対応
- 2.1 電子化に対するリスク
- 2.2 電子記録に対する規制要件
- 2.3 真正性の要件実現のための主な3つの対応
- 2.4 データインテグリティに対する規制要件
- 3.業務プロセスの電子化
- 3.1 完全電子化への可能性・難しさ
- 3.2 電子化への追い風と阻害要因
- 3.3 電子化検討における考え方
- 3.4 GMP工場における完全電子化の例
- 4.電子文書と電子化文書
- 4.1 電子文書
- 4.2 電子化文書
- 4.3 電子化検討の準備
- 4.4 電子文書 (電子データ) 運用・保管管理のポイント
- 4.5 電子文書 (電子データ) 生成システム更新時のデータに対するポイント
- 4.6 電子化文書の作成
- 5.電子化文書の運用管理における注意点
- 5.1 手順化
- 5.2 保管・管理
- 5.3 紙文書の廃棄
- 5.4 原本の重要性
2節 手順書・記録書におけるDI対策
- 1.医薬品の品質を保証するということ
- 1.1 重大な法令違反 (記録の改竄、隠蔽)
- 2.データインテグリティとは
- 2.1 データインテグリティに関する規制
- 2.2 ALCOA+の原則
- 2.3 紙ベース記録でデータインテグリティを確保するために
- 3.GMP文書・記録管理の基本
- 3.1 GMP手順書 (SOP) の作成
- 3.2 最新版管理
- 3.3 配付管理
- 3.4 GMP文書・記録の保管
- 4.製造記録と試験記録
- 4.1 生データの扱い
- 4.2 ダブルチェック
- 4.3 GMPにおける記録記入のポイント
- 4.4 訂正方法のポイント
- 4.5 押印かサインか?
- 5.GMP調査での指摘事項例
3節 製造部門で注意すべきDI対応のポイント
- 1.製造部門が管理する文書
- 1.1 GMP省令第10条
- 1.2 施行通知
- 1.3 GMP事例集
- 2.データインテグリティ (DI) の確保
- 2.1 GMP施行通知
- 2.2 GMP事例集
4節 試験検査室で注意すべきDI対応のポイント
- 1.当局査察の試験検査室のDIに関連した指摘事例
- 1.1 PMDA
- 1.2 FDA
- 2.用語の定義
- 3.DIに関連したガイダンス等
- 4.ガイダンスみる試験検査室におけるDI対応
- 4.1 データガバナンス
- 4.2 データの重要度
- 4.3 データリスク
- 4.4 データガバナンスシステムレビュー
- 4.5 組織文化
- 4.6 品質文化
- 4.7 パフォーマンス指標 (品質指標を含む) の定期的なマネジメントレビュー
- 4.8 一般的なDIの原則と実現方法
- 4.9 真性コピー
- 4.10 紙ベースの場合におけるDIの考慮事項
- 4.11 コンピュータ化されたシステムにおけるDIに特有な考慮事項
- 5.スプレッドシートのDI対応
- 5.1 DIの観点からみたスプレッドシートの問題点
- 5.2 スプレッドシートのDI対応
5節 記録の電子化でデータインテグリティを確保する取り組み
- 1.データインテグリティ確保への取組み
- 2.紙記録と電子記録の比較
- 3.電子記録の選定
- 4.記録の電子化へ向けた検討
- 5.システム要件の検討
- 6.システム開発方法
- 7.システム開発/導入のポイント
6節 DIに対応した生データの取り方・管理のポイント
- 1.生データとDI
- 1.1 生データとは
- 1.2 生データの定義は
- 1.3 DIと生データ
- 2.生データの取り方と管理
- 2.1 電子の生データを取得する際の注意事項
- 2.2 紙の生データを取得する際の注意事項
- 2.3 生データの確認と承認
- 2.4 生データの管理
7節 データインテグリティに関する従業員の教育訓練
- 1.データインテグリティ (DI) 教育の重要性
- 2.データインテグリティ (DI) 教育の種類
- 2.1 データインテグリティの本質:ALCOA原則から学ぶ
- 2.2 規制当局の指摘から学ぶ
- 2.3 ワークショップ形式で学ぶ
- 2.4 外部講師から学ぶ
第5章 改正GMP/国内外GMPで求められる交叉汚染の防止
1節 改正GMP省令における交叉汚染防止の要件
- 1.科学的な根拠にもとづく洗浄バリデーションの流れ
- 2.関連するPIC/Sガイドライン
- 2.1 全体概要
- 2.2 科学的な根拠に基づく洗浄バリデーションの方向性
- 2.3 交叉汚染防止に対する基本的な考え
- 2.4 専用化要件
- 3.今後の洗浄バリデーションの方向性
- 4.改正GMP省令における交叉汚染防止
- 4.1 改正省令
- 4.2 施行通知
- 5.改正GMP省令における専用化要件
- 5.1 改正省令
- 5.2 施行通知
- 6.「GMP省令が適用されない物品」の共用製造
- 6.1 改正省令
- 6.2 施工通知
- 7.GMP事例集 (2022年)
- 7.1 設備の共用に関連する項目
- 7.2 洗浄バリデーションに関連する項目
- 8.業界専門家団体からの関連ガイドライン
- 8.1 ISPE洗浄バリデーションガイド (2020年9月)
- 8.2 ASTM リスクベースアプローチにもとづく洗浄ガイドラインE3106-22
- 9.今後の洗浄バリデーションのプラクティス
2節 GMP工場内のHSEで求められる作業者の健康被害防止
- 1.HSE (健康・安全・環境) とGMPは両輪
- 1.1 GMPとHSEは生産活動の両輪とは
- 1.2 HSEで責任の所在を明確に
- 1.3 国際化に向けて対応できる工場に変革しましょう
- 1.4 HSE Global Standardの必要性
- 2.国内製薬企業の国際的な企業としての法律対応について
- 2.1 医薬品工場における現状
- 3.GMPなど各種法律の要件対応とHSE対応
- 3.1 あるべき姿
- 3.2 医薬品工場における現状
- 3.3 医薬品会社の社会貢献
- 4.GMPの無菌室管理とHSEの高活性曝露管理
- 4.1 製薬企業のあるべき姿
- 4.2 国内医薬品会社の現状
- 4.3 GMPとHSEの曝露管理情報比較表
- 5.GMPの無菌室管理とHSEの高活性曝露管理の運用上の重要性
- 5.1 製薬企業のあるべき姿
- 5.2 国内製薬企業の現状
- 5.3 これからの日本の製薬会社に期待すること
- 6.日本国内製薬企業の人材の多様性対応についての課題
- 6.1 製薬企業のあるべき姿
- 6.2 国内製薬企業の現状
- 6.3 これからの日本の製薬会社に期待すること
- 7.日本国内製薬企業に必要なGMP/HSEのサプライチェーンAudit
- 7.1 製薬企業のあるべき姿
- 7.2 国内製薬企業の現状
- 7.3 これからの日本の製薬会社に期待すること
- 8.日本国内製薬企業に必要なサプライチェーン従業員の健康管理
- 8.1 サプライチェーン従業員の健康管理の重要性とあるべき姿
- 8.2 GMPや化学物質など取り扱いリスク低減対策
- 8.3 リスクアセスメントに用いる情報と分析
- 8.4 化学物質曝露リスクアセスメント
- 8.5 リスクアセスメントのための分析
- 8.6 化学物質のリスクアセスメント評価方法
- 8.7 化学物質や医薬活性物質曝露リスク低減対策
- 9.国際化多様化社会におけるリスクアセスメントの重要性
- 9.1 国際化について
- 9.2 日本国内の国際化に対応するリスクアセスメントの現状
- 9.3 日本国内の工場・試験室・事務所の現状課題
- 9.4 日本国内企業に求められる国際的リスクアセスメントのあるべき姿
- 9.5 化学物質、製薬業界でのサプライチェーンマネジメント
3節 交叉汚染防止のための許容値 (PDE/AI) 設定・毒性評価法
- 1.許容一日曝露量 PDE (Permitted Daily Exposure)
- 1.1 PDEの設定手順
- 2.許容摂取量 AI (Acceptable Intake)
- 2.1 AIの設定手順
- 3.医薬品不純物の有害性評価値設定における留意事項
- 3.1 毒性情報が十分にない場合の有害性評価値の設定
- 3.2 PDEとAIの関係
- 3.3 有害性評価値を設定する者の適格性
4節 改正GMPをふまえた洗浄バリデーションと設備共用の可否判断のポイント
- 1.改正GMP省令と洗浄バリデーション
- 1.1 バリデーション指針について
- 1.2 改正GMP省令
- 2.毒性学的評価による洗浄バリデーション
- 2.1 留意点
- 2.2 洗浄バリデーションの手順
- 2.3 残留許容基準値 (限度値) の設定
- 2.4 毒性学に基づく洗浄バリデーションと残留許容基準
- 3.高生理活性物質と一般薬との洗浄バリデーションと設備共用の可否判断
- 3.1 残留許容値の設定と交叉汚染防止対策とリスクマネジメント
- 3.2 専用設備化の例外規定
- 3.3 医薬品の分類と設備専用化の判断基準
5節 PIC/S GMP Annex1に寄与する無菌医薬品の微生物試験とそのバリデーション
- 1.PIC/S GMP Annex1におけるCCSと微生物試験
- 2.無菌医薬品の微生物試験の概要
- 2.1 微生物試験の目的
- 2.2 微生物試験の分類
- 2.3 PIC/S GMP Annex1の各項目に寄与する微生物試験
- 3.PIC/S GMP Annex1に寄与する無菌医薬品の微生物試験とバリデーション
- 3.1 消毒剤の効果試験
- 3.2 環境モニタリング
- 3.3 培地充填試験
6節 製薬用水管理に関する規制動向とGMP管理項目
- 1.製薬用水システムの水質検査
- 2.USPの大きな改訂
- 2.1 Water conductivity 3-Stage-method
- 2.2 TOTAL ORGANIC CARBON
- 3.USP改正に対する日本薬局方からのコメント
- 4.日本薬局方での製薬用水に関する大きな改正
- 5.導電率測定
- 5.1 導電率計測定の目的
- 5.2 導電率一律管理と問題点
- 6.TOC測定について
- 6.1 TOCとは何か
- 6.2 TOCを測定する意義
- 7.JPにおけるTOC記述 (JP15まで)
- 8.JP16改正における有機体炭素試験
- 9.USPとJPにおけるTOC測定範囲に関連して
- 9.1 リアルタイムリリース試験へのTOC測定対応
- 9.2 センサーの比較試験
- 9.3 TOCを管理する意義は
- 9.4 TOCによる水質管理
- 10.膜WFIが世界中で注目される背景
- 11.日本での省エネ視点のさきがけ
- 12.3極薬局方における膜WFIへの認識の変化
- 12.1 EUの状況
- 12.2 米国の状況
- 12.3 日本の状況
7節 製薬用水におけるBurkholderia cepacia Complexの問題とその汚染管理戦略 (CCS) の構築
- 1.BCCが患者や非無菌製剤にもたらすリスク
- 1.1 BCCが患者や非無菌製剤にもたらすリスク:
- 1.2 どのような非無菌製剤がBBCに汚染されやすいか:
- 2.BCCについて
- 2.1 BCCとは
- 2.2 BCCの生物学的特性・性質:
- 3.バイオフィルムの形成と製薬用水からのBCCの検出
- 3.1 バイオフィルムについて
- 3.2 バイオフィルムの形成過程
- 3.3 製薬用水からのBCCの検出
- 4.バイオフィルムを抑制するための汚染管理戦略 (CCS)
- 4.1 バイオフィルムが形成されるリスクの特定
- 4.2 特定されたリスクに対する低減策
8節 改正GMPが空調設備に求める交叉汚染防止要件とその管理
- 1.医薬品工場向けクリーンルーム4原則
- 1.1 交叉汚染を防止するために、塵埃を持ち込まない
- 1.2 交叉汚染を防止するために、塵埃を発生させない
- 1.3 交叉汚染を防止するために、塵埃を堆積させない
- 1.4 交叉汚染を防止するために、塵埃を排除する
- 2.GMP要件に対する管理項目と維持技術
- 2.1 室外への持ち出しを空調設備により防ぐ (室圧・室間差圧)
- 2.2 医薬品工場の種類とその室圧・室間差圧・気流方向の特徴
- 2.3 交叉汚染を防ぐための空調設備
- 2.4 交叉汚染を防ぐための室圧・室間差圧・気流方向 (室圧・室間差圧を維持するために)
- 2.5 交叉汚染を防ぐための維持管理
第6章 不純物に対する規制と求められる管理戦略
1節 ICH Q (Q3C、Q3D) の動向と対応の要点
- 1.日本薬局方収載医薬品に係る残留溶媒の管理
- 1.1 残留溶媒の一般的留意事項
- 1.2 残留溶媒の管理に関する基本的な考え方
- 2.日本薬局方収載医薬品に係る元素不純物の管理
- 2.1 医療用医薬品に係る元素不純物の取扱い (2020年12月28日 厚生労働省発出)
- 2.2 要指導医薬品及び一般用医薬品に係る元素不純物の管理に関する基本的な考え方 (2022年12月12日 厚生労働省発出)
- 2.3 第一追補告示前に既に承認されている品目の取扱い (2022年12月12日 厚生労働省発出)
- 2.4 第一追補告示後に新規承認申請する品目の取扱い (2022年12月12日 厚生労働省発出)
- 2.5 第十八改正日本薬局方における元素不純物管理の取込みに伴う医薬品各条からの重金属試験及び個別金属不純物試験の削除
- 3.残留溶媒ガイドラインの改正ポイント
- 3.1 N-メチルピロリドン及びテトラヒドロフランの追加 (2002年12月25日厚生労働省発出)
- 3.2 クメンの追加 (2011年2月21日厚生労働省発出)
- 3.3 トリエチルアミン及びメチルイソブチルケトンの追加 (2018年7月19日厚生労働省発出)
- 3.4 2-メチルテトラヒドロフラン,シクロペンチルメチルエーテル及びターシャリーブチルアルコールの追加 (2021年8月13日厚生労働省発出)
- 3.5 残留溶媒の分析方法
- 4.元素不純物ガイドラインの改正ポイント
- 4.1 カドミウムの吸入暴露時PDE値算出方法の見直しに伴う数値等の修正
- 4.2 金,銀,ニッケルのPDE値の修正
- 4.3 皮膚及び経皮曝露の元素不純物の限度値 (付録5) の追加
2節 ICH M7 (変異原性不純物) の要点と求められる不純物管理
- 1.原薬の重要品質特性 (CQA; Critical Quality Attributes)
- 2.物質特性及び工程パラメータと原薬CQAとの関連付け
- 3.合成原薬の出発物質の選定の妥当性
- 4.ライフサイクルマネジメント
- 5.M7ガイドラインの適用範囲
- 6.一般原則
- 7.Q11と不純物
- 8.市販製品に関する検討事項
- 8.1 原薬の化学、製造及び管理に対する承認後の変更
- 8.2 製剤の化学、製造及び管理に対する承認後の変更
- 8.3 市販製品の臨床使用に対する変更
- 8.4 市販製品に関するその他の検討事項
- 9. 原薬及び製剤中の不純物に関する評価
- 9.1 合成不純物
- 9.2 分解生成物
- 9.3 臨床開発に関する検討事項
- 10.ハザード評価の要件
- 11.リスクの特性評価
- 11.1 TTCに基づく許容摂取量
- 11.2 化合物特異的なリスク評価に基づく許容摂取量
- 11.3 一生涯より短い期間 (LTL) の暴露に関する許容摂取量
- 11.4 複数の変異原性不純物に関する許容摂取量
- 11.5 アプローチの例外及び柔軟性
- 12.管理
- 12.1 製造工程由来不純物の管理
- 12.2 管理方法の検討事項
- 12.3 定期的試験に関する検討事項
- 12.4 分解生成物の管理
- 12.5 ライフサイクルマネジメント
- 12.6 臨床開発に関する検討事項
- 13.ドキュメンテーション
- 13.1 治験届
- 13.2 コモンテクニカルドキュメント (製造販売承認申請)
- 14.遺伝毒性不純物
- 15.アラート構造
- 16.ニトロソアミン類の問題と規制当局への対応
3節 原薬中のニトロソアミン類の管理
- 1.ニトロソアミン類とは
- 1.1 ニトロソアミン類
- 1.2 食品中の有害化学物質として注目されるようになった経緯
- 1.3 食品中のニトロソアミン類の生成経路
- 1.4 ニトロソアミン類に懸念される毒性
- 2.「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検」
- 2.1 対象となる医薬品
- 2.2 自主点検の基本的な考え方
- 2.3 確認事項、実施期限等について
- 2.4 承認申請中又は承認申請前の品目について
- 2.5 製造販売業者以外の業者の対応について
- 2.6 その他
- 3.「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検」に関する質疑応答集 (Q&A)
- 4.原薬中のニトロソアミン類の管理
4節 製剤中のニトロソアミン類の管理
- 1.ニトロソアミン類混入問題の背景
- 2.製剤中でのニトロソアミン類混入に関するリスク評価,確認の試験,リスク緩和措置
- 2.1 ニトロソアミン類の混入に関するリスク評価 (Step1)
- 2.2 確認の試験 (Step2)
- 2.3 リスク緩和措置 (Step3)
5節 In silicoによる医薬品からのN-ニトロソアミン類の生成リスク評価
- 1.In silico手法による不純物の管理
- 2.医薬品の分解物生成物予測
- 2.1 Pharma D3
- 2.2 CAMEO
- 2.3 DELPHI
- 2.4 ZenethR
- 3.分解生成物予測ソフトウェアによる分解物の生成経路予測
- 3.1 ラニチジンからのニトロソアミンの生成経路予測
- 3.2 グリクラジド/インダパミドからのニトロソアミンの生成経路予測
6節 元素不純物の試験法設定及びバリデーションの事例
- 1.元素不純物及びバリデーションに関するガイドライン
- 1.1 元素不純物試験のバリデーション
- 2.元素不純物試験における試験法設定
- 2.1 濃度限度値の算出
- 2.2 前処理方法の検討
- 2.3 希釈倍率の決定
- 2.4 (適格性) 確認試験の実施
7節 ニトロソアミン類混入を防ぐ原料資材メーカーの選定・監査
- 1.ニトロソアミン類とは?
- 1.1 ニトロソアミン類の生成
- 1.2 ニトロソアミン類の毒性
- 2.ニトロソアミン類に対する規制当局の動き
- 2.1 欧州医薬品庁 (EMA)
- 2.2 米国食品医薬品局 (FDA)
- 2.3 厚生労働省 (日本)
- 3. 原料資材メーカーの選定
- 3.1 原料資材メーカーの選定プロセス
- 3.2 リスク評価
- 3.3 原料資材メーカーの監査
8節 E&L (Extractables&Leachables) に関する規制・ガイドラインと評価法の実際
- 1.はじめに
- 2.ICH Q3Eガイドライン
- 3.具体的なガイドライン
- 4.対象となる医薬品とリスクファクター
- 5.各種プラスチックの製造の流れ
- 6.抽出物、浸出物の定義
- 7.抽出物、浸出物の評価の手順
- 8.PQRIによる抽出物、浸出物の評価手順
- 8.1 情報収集と有害物質の選出
- 8.2 抽出条件の検討、抽出物試験、リスト化
- 8.3 リスクアセスメント:安全性、毒性評価
- 8.4 浸出物試験:検出、同定、定量
- 9.抽出物、浸出物の分析
- 10.様々な機器分析とその抽出法
- 10.1 GC/MSの代表的なサンプル前処理法溶媒抽出法
- 10.2 LC/MS代表的なサンプル前処理法溶媒抽出法
- 10.3 GC/MSによる分析
- 10.4 LC/MSによる分析
- 10.5 プラスチック中の添加剤の保持時間をシミュレーションするソフトウェア
9節 医薬品製造におけるエンドトキシン管理の要件とDI対応
- 1.リムルステストによるエンドトキシン測定法
- 2.リムルステストの特異性とエンドトキシン測定法の進歩
- 3.エンドトキシン管理の要件
- 3.1 エンドトキシン規格値の設定
- 3.2 エンドトキシン試験の実施
- 3.3 エンドトキシン汚染の防止とエンドトキシン除去
- 4.エンドトキシン試験のバリデーション
- 4.1 本バリデーションが重要である理由
- 4.2 本バリデーションと試験の手順
- 5.エンドトキシン試験とDI
- 5.1 DI確保に必要な要件
- 5.2 DIの重要な要素
- 5.3 コンピュータ化システムバリデーション (CSV)
- 5.4 エンドトキシン試験における生データとメタデータ
- 5.5 DIとLIMS
- 5.6 エンドトキシン測定・管理のプロセスとDI
- 6.エンドトキシン試験法の代替法
第7章 医薬品工場のDX推進とGMP・DIへの対応
1節 医薬品工場におけるIoT活用・生産の自動化とDI対応
- 1.医薬品工場における IoT 活用・生産の自動化
- 1.1 デジタル化された医薬品工場の成熟モデル
- 1.2 連続生産とリアルタイム出荷
- 2.医薬品工場における DI 対応
- 2.1 DIの要件
- 2.2 ALCOAとCCEA (ALCOA+)
- 2.3 データライフサイクルについて
- 2.4 ITシステムの基盤整備とリスクベースドアプローチ
- 2.5 DIにおける当局要求・不適合事例
- 3.推奨事項
- 3.1 構想策定の重要性
- 3.2 拡張現実 (XR) の重要性
- 3.3 コンピュータ化システムバリデーション
2節 DX推進に伴う生産データの取得・蓄積と最大活用
- 1.医薬品生産のデジタル化の社会的・経営的な意義
- 2.包括的な管理戦略の実現 部門の連携・データの収集・ルールへの変換
- 3.生産プロセスのデジタル化、データ活用
- 3.1 モノづくりの高度化のケーススタディ
- 3.2 細胞医薬品のデータ活用の展望
- 4.データ活用のプラットフォームづくりの要点
- 4.1 非機能要件への対応
- 4.2 モデルの検証・運用
- 4.3 組織づくり・人づくり・データ活用の手順づくり
3節 PAT技術のリアルタイムモニタリングによる製造工程の解析および品質管理
- 1.画像解析システムによる撹拌造粒のリアルタイム計測、終点制御および品質管理
- 1.1 画像解析システムおよび実験方法
- 1.2 リアルタイム計測,粒径dv50と篩分け法dw50の比較,および平均粒子径の再現性
- 1.3 平均粒子径と結合水添加速度
- 1.4 工程パラメータと画像制御終点でのdv,e50および整粒後のds
- 2.近赤外分光法による錠剤の高速全数識別,および異種錠検査と品質管理
- 2,1 採用した装置の特徴
- 2.2 処方,打錠および含量測定
- 2,3 リアルタイム測定による異種錠剤の検知・識別
- 2.4 錠剤全数のリアルタイム含量測定および評価
4節 製薬業界におけるデジタルツインと工場の最適化
- 1.従来の手法
- 2.スマートマニファクチャリングの必要性
- 2.1 スマートマニファクチャリングで将来に備える
- 2.2 生産効率の向上
- 2.3 デジタルツインを活用して生産パフォーマンスを改善
- 3.ラインプランニングソリューション
- 4.成功事例
5節 バイオ医薬品における品質評価の自動化・DX化
- 1.アジレントのバイオ医薬品の品質評価に関連する製品群の紹介
- 2.メソッド作成自動化
- 3.分析ラボのデジタル化
6節 DXによる品質保証の効率化への取り組み
- 1.SHIONOGIが目指す品質保証の在り方
- 2.Global QA Harmonization Projectにおける課題
- 3.Global QA Harmonization Projectの成果と将来的な展望
7節 産業間比較から考えた医薬品工場のさらなるスマート化
- 1.<スマートである>とは
- 2.製造業と工場のデータの流れ
- 3.工場の産業間比較:プロセス対ディスクリート
- 4.IoT技術のインパクトとMES/MOMの役割
- 4.1 IoT技術のインパクトとは
- 4.2 MES/MOMシステムの意義と役割
- 4.3 MES/MOMシステムの機能範囲
- 4.4 医薬品工場の位置づけ
- 5.工場の未来像と「中央管制システム」
8節 ラボ用TOC測定の自動化とDI対応
- 1.TOC測定とその役割
- 2.主なラボ用TOC測定装置の酸化方式
- 2.1 湿式紫外線 (UV) 酸化方式
- 2.2 燃焼酸化方式
- 3.ラボ用TOC測定における自動化
- 3.1 キャリーオーバー対策の自動化
- 3.2 日常点検試験と測定プロセスの自動化
- 4.ラボ用TOC測定のDI対応
- 4.1 PCや専用ソフトが不要
- 4.2 データの完全性対応
- 4.3 ID,パスワード,権限設定,監査証跡への対応
- 4.4 バックアップ、リストア機能
第8章 連続生産の規制対応と管理戦略・プロセス構築
1節 ICH Q13の概要と原薬の連続生産プロセスの開発/管理戦略
- 1.ICH Q13
- 1.1 化学薬品原薬のCMの例 (ICH Q13付録I)
- 1.2 CM特有の管理戦略と展望
- 2.原薬のCM
- 3.連続晶析の観点から
- 3.1 連続晶析とバッチ晶析
- 3.2 MSMPR晶析装置による連続晶析
- 3.3 MSMPR晶析装置のカスケード運転
- 3.4 晶析操作における核化と結晶成長の分離
2節 固形製剤における連続生産プロセスの管理戦略
- 1.管理戦略
- 2.CMプロセスの特徴
- 3.CMプロセスの管理戦略のオプション
- 4.管理戦略構築のステップ
- 4.1 機器の設計,構成,統合
- 4.2 原料特性評価と適合性チェック
- 4.3 RTDモデルの実装
- 4.4 リスク分析
- 4.5 工程モニタリング及び管理
- 4.6 プロセスモデル
- 4.7 工程確認
3節 プロセスモニタリング技術の構築と活用
- 1.ソフトセンサーとは
- 2.ソフトセンサーの適用先
- 3.ソフトセンサーの役割
- 4.ソフトセンサーの運用までの流れ
- 5.ソフトセンサーの課題と今後
4節 プロセスシミュレーションを通じたバッチプロセスと連続プロセスの相違点理解
- 1.はじめに
- 2.プロセスシミュレーション
- 2.1 基礎現象 (物理化学) と複合操作としての単位操作
- 2.2 装置設計問題と操作設計問題
- 3.バッチプロセスと連続プロセスの特徴
- 3.1 プロセスの特徴に応じたバッチと連続プロセスの選択評価項目
- 3.2 医薬品連続プロセスの導入動機
- 3.3 数理モデルによるバッチプロセスと連続プロセスの表現形式
- 4.シミュレーション事例を通じた相違点理解
5節 リアルタイムモニタリング技術による連続生産の最適化
- 1.連続フロー生産とPAT
- 1.1 連続フロー反応の分析手法
- 1.2 PATとは?
- 1.3 in situ リアルタイム FTIR ReactIR
- 2.ラボでのPATの活用
- 2.1 ラボでの初期検討の必要性
- 2.2 活用事例 – One Step Synthesis of Substituted Indazoles –
- 3.商業生産でのPATの活用
- 3.1 PATによるリスク回避
- 3.2 6-Hydroxybuspironeの製造のための安全でスケーラブルで連続的なプロセスの開発
6節 造粒乾燥工程から打錠工程までの連続化の取り組み事例
- 1.連続生産プロセスの概要
- 1.1 医薬品の連続生産とバッチ生産の比較
- 1.2 ICH-Q13ガイドラインに基づく固形製剤連続生産の技術的側面とポイント
- 1.3 全体フロー
- 2.各装置選定及び注意点
- 2.1 造粒乾燥機の選定
- 2.2 混合機の選定
- 2.3 打錠機の選定
- 3.システム構築におけるエンジニアリング要素
- 3.1 全体工程の制御
- 3.2 工程間の粉体輸送
- 3.3 サージホッパーの適用
- 3.4 ロスインウェイトフィーダー
- 3.5 検査選別装置 iSorterR
7節 直打連続生産システムを用いた微量含量錠剤の製造
- 1.直打連続生産システム構成
- 1.1 定量フィーダPOLARIS (ポラリス)
- 1.2 原料投入用垂直混合機 CRATERI (クラーテルI)
- 1.3 水平混合機【ARIES】
- 1.4 最終混合用垂直混合機【CRATERII】
- 2.微量連続混合実験2)
- 2.1 供給速度の評価
- 2.2 薬物と乳糖一水和物の混合実験
- 3.直打連続生産システムを使用した微量含量錠剤製造実験
- 3.1 薬物と各種添加剤との連続混合および打錠実験
8節 バイオ医薬品における連続生産プロセスの構築と品質管理
- 1.バイオ医薬品の連続生産
- 1.1 バイオ医薬品の連続生産の歴史、特徴など
- 1.2 バイオ医薬品の連続生産の技術と課題
- 1.3 バイオ医薬品の連続生産の規制対応のポイント
9節 連続ロセス構築への機械学習の活用~フロー合成の事例
- 1.機械学習利用の観点からみたフロー合成法の特長
- 2.PATを利用したデータ取得
- 3.ベイズ最適化によるフロー合成条件の最適化
- 4.自動フロー合成プラットフォームによるハイスループットデータ取得
- 5.フロー合成-PAT統合システムと機械学習の併用
- 5.1 多段階反応に対するPAT-機械学習利用によるリアルタイム解析
- 5.2 モジュール型フロー合成-PAT統合システムによる自動最適化
出版社
お支払い方法、返品の可否は、必ず注文前にご確認をお願いいたします。
体裁・ページ数
A4判 667ページ
ISBNコード
978-4-86798-041-5
発行年月
2024年9月
販売元
tech-seminar.jp
価格
80,000円 (税別) / 88,000円 (税込)
これから開催される関連セミナー
関連する出版物
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2013/5/30 | 新薬開発にむけた臨床試験(第I~III相臨床試験)での適切な投与量設定と有効性/安全性評価 |
| 2013/5/20 | ドラッグデリバリーシステム 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2013/5/20 | ドラッグデリバリーシステム 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
| 2013/3/27 | 医薬品・食品包装の設計と規制・規格動向 - 品質・安全・使用性向上のために - |
| 2013/2/5 | 放射線医療(癌診断・治療) 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
| 2013/2/5 | 放射線医療(癌診断・治療) 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2013/1/28 | 造粒・打錠プロセスにおけるトラブル対策とスケールアップの進め方 |
| 2012/9/4 | 食と健康の高安全化 |
| 2012/3/13 | 超入門 GMP基礎セミナー |
| 2012/3/5 | 育毛剤・発毛剤 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2012/2/16 | システムの適格性確認および回顧的バリデーションの具体的実施方法 |
| 2012/2/14 | LIMS導入に関する導入の留意点セミナー |
| 2012/2/9 | 厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理GL」対応のための「回顧的バリデーション」および「リスクアセスメント」実施方法 |
| 2012/1/30 | 水処理膜の製膜技術と材料評価 |
| 2012/1/20 | 24年度診療報酬改定におけるDPC評価の全貌 |
| 2011/12/22 | 光学活性医薬品開発とキラルプロセス化学技術 |
| 2011/12/14 | QCラボにおける厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理GL」対応セミナー |
| 2011/12/10 | 製薬大手5社 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2011/12/8 | 最新のCSV動向および21 Part 11も視野に入れたFDA査察対応方法 |
| 2011/11/7 | eCTD申請 「-ここまで身近になったeCTD申請-」 |