技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
封止・バリア・シーリングに関する材料、成形製膜、応用の最新技術
オンデマンド版: 5G機器、次世代自動車 、IoT機器や未来の蓄電デバイスを支える
封止・バリア・シーリングに関する材料、成形製膜、応用の最新技術
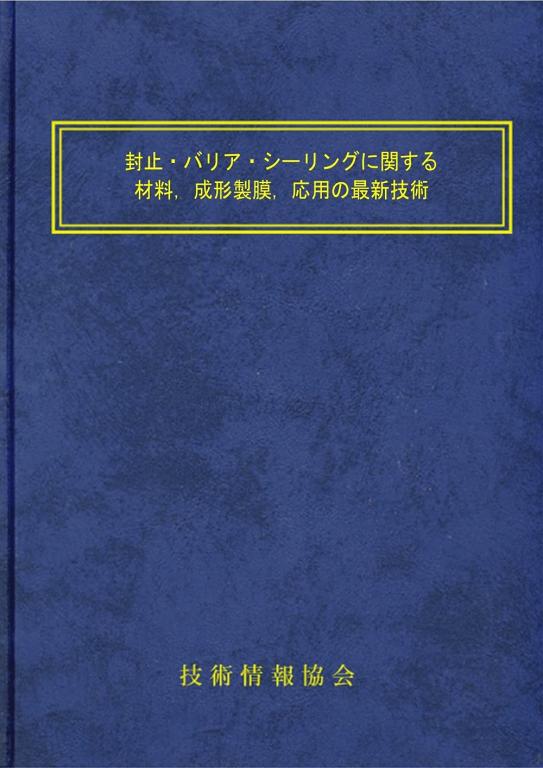
目次
第1章 封止、バリア、シーリング技術の概要
第1節 封止、バリア、シーリング技術の概要
- 1.封止技術
- 2.バリア技術
- 3.シーリング技術
第2章 封止材および周辺材料とその材料設計
第1節 封止材に用いられるエポキシ樹脂の合成・樹脂設計について
- 1.一般的なエポキシ樹脂の合成方法
- 2.電気信頼性の向上
- 3.耐熱性 (ガラス転移点) の向上
- 4.耐熱分解性の向上
- 5.熱伝導性の向上
第2節 封止材に用いられるエポキシ樹脂の合成および樹脂設計、その高機能化
- 1.高Tgエポキシ樹脂
- 2.高耐湿性可撓性エポキシ樹脂
- 3.エステルフリー脂環式エポキシ樹脂
第3節 フィラーによるエポキシ樹脂封止材の高熱伝導化 低熱膨張化技術
- 1.無機フィラーの種類と特徴
- 2.高熱伝導フィラーの設計
- 3.低熱膨張フィラーの設計
第4節 各種エポキシ樹脂硬化剤の種類と特徴および最適選定
- 1.エポキシ樹脂硬化剤の種類
- 1.1 アミン系硬化剤
- 1.1.1 脂肪族アミン
- 1.1.2 芳香族アミン
- 1.2 酸無水物系硬化剤
- 1.3 フェノール系硬化剤
- 1.4 潜在性硬化剤
- 1.1 アミン系硬化剤
- 2.エポキシ樹脂硬化剤の特徴
- 3.応用分野別の要求特性に応じた硬化剤の選択
第5節 酸無水物系硬化剤の特徴と機能性付与
- 1.酸無水物の種類と特徴
- 1.1 液状酸無水物
- 1.2 固形酸無水物
- 2.酸無水物使用時のポイントおよび注意事項
- 2.1 酸無水物配合量の最適化
- 2.2 吸湿による酸無水物の特性低下
- 3. 硬化物性の改善
- 3.1 耐熱性の改善
- 3.2 透明性の付与
- 3.3 耐湿性の改善
- 3.4 可撓性の改善
- 3.5 薄膜硬化性の改善
- 4.安全衛生上の留意
第6節 靭性に優れた高耐熱ビスマレイミド樹脂の開発と応用
- 1.チオール変性ビスマレイミド樹脂
- 2.ポリロタキサン変性ビスマレイミド樹脂
- 3.封止材料への応用
第7節 低融点ガラスを用いたガラス封止技術
- 1.低融点ガラス
- 1.1 低融点ガラスの種類と特徴
- 1.2 低融点ガラス接着剤の製造方法
- 2.低融点ガラス封止製品
- 2.1 ディスプレイ
- 2.2 断熱ガラス
- 2.3 ミラー
第8節 粒子径、粒子径分布、粒子形状・表面状態の制御による充填性・流動性の改善
- 1.充填性の表現
- 2.粉体の充填性に及ぼす粒子径分布の影響
- 2.1 粉体の充填性に及ぼす粒子径の影響
- 2.2 大小2成分粒子ランダム混合層の充填性
- 2.3 粉体の充填性に及ぼす粒子径分布の影響
- 2.4 粉体の充填性に及ぼす粒子間付着性の影響
- 3.粉体の充填性に及ぼす粒子形状の影響
- 3.1 粒子表面凹凸状態の計測と充填性に及ぼす影響
- 3.2 充填性に及ぼす粒子全体の形状の影響
- 4.粉体の充填性に及ぼす粒子表面改質の影
- 5.熱硬化性樹脂の流動性に対するフィラー粒子径分布の影響
第3章 バリアフィルム、ゲッター材、フレキシブル封止とその材料設計
第1節 高バリア樹脂EVOHの特性および開発とその応用について
- 1.EVOHの特徴と一般的性質
- 2.EVOHの成形加工と開発事例
- 2.1 EVOHの成形加工
- 2.2「エバール?」SPシリーズ
- 2.3「エバール?」APシリーズ
- 2.3.1 概要
- 2.3.2 特性
- 2.3.3 用途
- 3.食品包装材への応用
- 3.1 食品ロス削減に貢献するバリア材料
- 3.2 最適包装設計
- 4.バリア性の理論
- 4.1 ガス透過理論
- 4.2 溶解度パラメータ (SP値)
- 4.3 ポリマー構造
- 4.4 温度の影響
- 4.5 湿度の影響
- 5.バリア材料の貢献事例
- 5.1 包装による食品ロス削減、その他要望への貢献
- 5.2 缶・ビンのプラスチック化
- 5.3 穀物保存袋
第2節 粘土を用いた水蒸気バリア性耐熱性フィルム開発と応用展開について
- 1.水蒸気バリア膜
- 1.1 膨潤性粘土と粘土膜の製法
- 1.2 製膜メカニズム
- 1.3 ガスバリア性
- 1.4 水蒸気バリア性
- 2.耐熱絶縁膜
- 2.1 非膨潤性粘土を用いた耐熱絶縁膜
- 2.2 耐熱絶縁膜の製法
- 2.3 耐熱絶縁膜の特徴と用途
第3節 真空・圧空成形法を用いたバリア性を有するフィルム封止とその応用
- 1.TOM工法のプロセス
- 2.TOM工法の特徴
- 3.応用事例
- 4.バリア性を有するTOM用フィルム
第4節 冷凍条件下の耐ピンホール性に優れたガスバリアフィルム
- 1.ヘプタックス
- 2.冷凍下での発生ピンホールと耐ピンホール性評価方法
- 3.ヘプタックス PFタイプの開発
- 4.実包評価による検証
- 5.PFタイプの特長
- 6.PFタイプの用途
第4節 電子部品パッケージにおけるゲッターやアクティブバリア剤の効果と応用
- 1.真空・希ガス置換ハーメチックパッケージ内のガス環境とゲッターによる吸着
- 1.1 ハーメチックパッケージ内のガス源
- 1.1.1 微小リークによりパッケージ内に侵入してくるガスによる内圧上昇
- 1.1.2 デバイスの構成部品やパッケージ材料、封止プロセス起因で発生するガス
- 1.2 ゲッターによるハーメチックパッケージ内のガス吸着
- 1.2.1 ゲッターとは
- 1.2.2 ゲッターの使用方法
- 1.2.3 ハーメチックパッケージ向けゲッターの種類
- 1.1 ハーメチックパッケージ内のガス源
- 2.セミハーメチックパッケージ内のガス環境とゲッターによる吸着
- 2.1 セミハーメチック内のガス環境
- 2.2 水分ゲッターによるセミハーメチックパッケージ内のガス吸着
- 2.2.1 水分ゲッターを使用する際のパッケージ構造
- 2.2.2 各構造に適した水分ゲッター
- 3.アクティブバリアシール剤による水分侵入抑制
第5節 有機EL素子用乾燥剤について
- 1.有機ELの不良拡大・成長
- 2.乾燥剤の種類
- 3.シート乾燥剤「HG-SHEET」
- 3.1 HG-SHEETの特徴〜吸湿剤〜
- 3.2 HG-SHEETの構造〜PTFE樹脂〜
- 3.3 HG-SHEETの構造〜粘着テープ〜
- 3.4 HG-SHEETの供給形態
- 4.ペースト乾燥剤「HG-PASTE」
- 4.1 HG-PASTEの特徴
- 4.2 ブリードアウト (ポンプアウト)
- 5.吸湿防止対策
- 5.1 製造環境
- 5.2 包装材料
第4章 シーリング材、防水防湿コーティングとその材料設計
第1節 柔軟性ホットメルトシーリング材の用途展開
- 1.従来の技術
- 2.材料開発
- 3.本製品の特長
- 4.ホットメルトアプリケーションシステム
第2節 光部品用の防湿・防水性を有する接着・シール技術
- 1.光部品の防湿封止用エポキシ系防湿接着シール材
- 1.1 光部品用防湿接着シール材の主な要求条件
- 1.2 開発された光部品用エポキシ系接着シール材の特性
- 1.3 光ファイバの光損失増の問題
- 1.4 耐湿接着性
- 1.5 透湿性
- 1.6 高温高湿環境下における光部品ケース内の湿度予測
- 1.7 新規光部品用防湿接着シール材の主な特性
- 1.8 熱硬化タイプのシール材の光部品への応用例4)
- 2.ファイバ融着接続部補強用の防水 (湿) 性熱溶融接着シール材
- 2.1 光ファイバ接続部補強用熱溶融接着シール材の主な要求条件
- 2.2 従来の熱溶融接着剤の特性
- 2.3 開発された光ファイバ接続部補強用反応性熱溶融接着シール材
- 2.4 開発されたシラン変性エチレン系熱溶融接着シール材の特性
- 2.4.1 接着性および耐水接着性
- 2.4.2 保存安定性
- 2.5 光ファイバ接続補強部への応用
- 2.5.1 開発熱溶融接着シール材を用いたファイバ接続補強部の耐水性
- 2.5.2 開発熱溶融接着シール材を用いたファイバ接続補強部の耐水信頼性
- 2.6 熱溶融接着シール材の光部品用防湿シール材への応用
- 2.6.1 ハイブリッド集積光送受信モジュールのパッケージング
- 2.6.2 LDモジュールの簡易気密実装
第3節 フッ素樹脂 (PVDF) の封止/保護/防水/防湿/バリア材などへの応用
- 1.PVDFについて
- 2.耐候性 (耐UV性)
- 3.耐薬品性
- 4.ガスバリア性
- 5.PVDFの耐候性、耐薬品性、ガスバリア性の応用
- 5.1 太陽電池への応用
- 5.1.1 太陽電池バックシートへの応用
- 5.1.2 太陽電池フロントシートへの展開
- 5.2 チューブ用途
- 5.2.1 産業用チューブ
- 5.2.2 自動車用チューブ
- 5.3フィルム用途
- 5.3.1 産業用フィルム
- 5.3.2 自動車内外装フィルム
- 5.1 太陽電池への応用
第4節 フッ素系防水・防湿コーティング剤を用いた防水処理の薄型化
- 1.フッ素系防水・防湿コーティング剤の調製とその静的・動的撥水性
- 1.1 塗膜成分である共重合体の作製
- 1.2 静的撥水性の評価
- 1.3 動的撥水性の評価
- 1.4 防湿性能
- 1.5 防錆性能
- 1.6 基本性能・製品特徴のまとめ
- 2.モバイル端末への適用を想定した性能評価
- 2.1 間隙の幅と水の侵入の関係
- 2.2 電気特性
- 2.3 長期性能評価
- 2.4 耐摩耗性能付与を付与したオプトエースの開発8)
第5節 TOM工法による革新的な防水技術
- 1.TOM工法による基板防水加工のプロセス
- 2.処理加工形態と完成品姿
- 3.この工法による特徴
- 4.他の防水工法との比較
- 5.将来に向けた展開
第6節 DLC膜の保護特性と撥水性・バリア性能
- 1.DLCとは
- 2.DLCの保護膜特性と用途
- 2.1 各種保護膜用途について
- 2.2 レンズ金型用保護膜
- 2.3 アルミニウム用保護膜
- 3.DLC膜の撥水性
- 3.1 機能性の付与
- 3.2 撥水性の制御
- 3.3 撥水性DLC膜の特性
- 4.電極・フィルム保護膜への応用
- 4.1 新規成膜方法
- 4.2 電極用保護膜
- 4.3 DLC膜のバリア性能
第7節 植物由来のゲル化剤と脂肪酸を用いた超撥水コーティング
- 1.超撥水コーティングの方法
- 2.超撥水表面の形成
- 2.1 HCOと脂肪酸の割合
- 2.2 超撥水表面の構造
- 2.3 脂肪酸の種類
- 3.摩耗した超撥水表面の経時変化
- 3.1 摩耗したサンプルの作製
- 3.2 経時変化
第5章 封止材料および封止プロセスの高度化による基板および接合部の機能性向上
第1節 半導体封止材料における界面のコントロール
- 1.半導体パッケージ中の界面のコントロール
- 2.半導体封止樹脂中の界面のコントロール
- 2.1 半導体封止樹脂の強度
- 2.2 高強度化と低吸水率化へのシランカップリング剤の効果
第2節 各種高分子材料のヒートシールによる封止技術
- 1.高分子材料の加工とヒートシール
- 1.1 ヒートシールする高分子材料
- 1.2 ガラス転移
- 1.3 高分子の結晶化
- 2.各種高分子のヒートシール技術と接合のメカニズム
- 2.1 ヒートシールに適する高分子材料:結晶化しやすい高分子
- 2.2 ヒートシールの難しい高分子材料1:結晶化しにくい高分子
- 2.3 ヒートシールの難しい高分子材料2:結晶化しない高分子
- 2.4 ヒートシールと結晶化度
- 2.5 ヒートシールのメカニズムの多様性
第3節 インサート材を用いた異種材料のレーザ接合技術と製品への応用について
- 1.インサート材を用いたレーザ接合技術
- 1.1 開発プロセスの特徴
- 1.2 プラスチックとの接合
- 1.3 金属との接合
- 2.製品への応用
- 2.1 スマートフォンへの採用
- 2.2 異種金属間の接合
- 2.3 熱可塑性CFRPの接合
第4節 赤外線を使用した異種材料の接合技術
- 1.樹脂カシメの工法
- 2.赤外線カシメのプロセス
- 3.他工法と比較した場合の赤外線カシメ
- 3.1 ワークへのダメージ
- 3.2 ランニングコスト
- 3.3 サイクルタイム、ダウンタイム
- 3.4 カシメ強度と安定性
第5節 ガラスモールド技術と成形機について
- 1.ガラスモールドとは
- 2.型
- 3.成形技術
- 4.ガラスモールド成形機
第6章 封止材料および基板との接合部における熱的特性、電気的特性のコントロール
第1節 エポキシ樹脂 の設計と高耐熱・高透明性技術
- 1.脂環式エポキシ樹脂の合成法
- 1.1 脂環式エポキシ樹脂の種類と性状
- 1.2 脂環式エポキシ樹脂の反応性と硬化物物性
- 1.2.1 脂環式エポキシ樹脂の反応性
- 1.2.2 酸無水物の硬化物物性
- 1.2.3 熱カチオンの硬化物物性
- 1.2.4 UVカチオンの硬化物物性
- 1.2.5 フェノール 樹脂 の硬化物物性
- 1.3 脂環式エポキシ樹脂の代表的な用途
- 1.4 脂環式エポキシ樹脂の高耐熱の取組について
- 1.5 脂環式エポキシ樹脂の高透明の取組について
第2節 エポキシ樹脂の分子設計と耐熱性、放熱性向上技術
- 1.高温耐久性向上技術
- 2.熱伝導性向上技術
第3節 高熱伝導性高分子材料の設計指針と開発の現状
- 1 高放熱性高分子材料への期待
- 2 高分子自身の高熱伝導化
- 3 高分子材料の複合化による熱伝導率の向上
- 3.1 粒子分散複合材料の熱伝導率に与える影響9-22)
- 3.2 影響因子を踏まえた高熱伝導化方法
- 3.2.1 従来から行われている改善方法
- 3.2.1.1 ファイバー状及び板状の充填材の使用
- 3.2.1.2 充填材の粒度分布の工夫24)
- 3.2.2 最近開発された改善方法
- 3.2.2.1 充填材の連続体形成量の増大
- 3.2.2.2 充填材を連続相に
- 3.2.2.3 充填材の接触面を増大し、完全な連続相に
- 3.2.2.4 ダブルパーコレーションの利用
- 3.2.2.5 多種の粒子の利用
- 3.2.2.6 複合液晶性高分子材料の熱伝導率
- 3.2.2.7 フィラー同士を融着し、共連続構造を形成した高熱伝導性樹脂
- 3.2.2.8 フィラーの表面修飾の工夫で、石英よりも小さい熱膨張率を併せ持つ高熱伝導性樹脂
- 3.2.2.9 充填材の熱伝導率の増大
- 4.相反機能関係の解消に向けて
- 4.1 柔軟性との相反関係解消
- 4.1.1 凹凸面における熱抵抗とその評価と低減法
- 4.1.2 平面における熱抵抗とその評価
- 4.2 加工性との相反関係解消
- 4.2.1 柔軟材等を活用した高熱伝導性プラスチック
- 4.2.2 高熱伝導性プラスチックの成形加工での注意点
- 4.1 柔軟性との相反関係解消
- 5.応用分野と将来展望
第4節 エポキシ樹脂など高分子の絶縁破壊・劣化のメカニズム
- 1. 絶縁破壊のメカニズム
- 1.1 絶縁破壊電界の特性
- 1.2 絶縁破壊の基礎理論
- 1.2.1 概観
- 1.2.2 電子的破壊機構
- 1.2.3 純熱的破壊
- 1.2.4 電気機械的破壊
- 2. 絶縁劣化のメカニズム
- 2.1 絶縁劣化の概観
- 2.2 電圧印加によって引き起こされる絶縁劣化
- 2.2.1 部分放電劣化
- 2.2.2 トリーイング (電気トリーと水トリー)
- 2.2.3 トラッキング
- 2.2.4 エレクトロケミカルマイグレーション (イオンマイグレーション)
第5節 封止材に用いられるエポキシ樹脂の劣化の実例
- 1. 研究成果の紹介
- 1.1 軟質エポキシ樹脂と硬質エポキシ樹脂
- 1.2 熱・放射線同時劣化処理
- 1.3 熱的特性
- 1.4 力学的特性
- 1.5 誘電的特性
- 1.6 実験結果のまとめ
第6節 液体誘電体の新規開発による環境適合型絶縁設計技術 〜沿面放電現象の把握〜
- 1.供試絶縁油と物理的・電気的特性 (新油と熱加速劣化油)
- 2.絶縁油/油浸プレスボード界面の交流沿面放電特性
- 2.1 油中沿面放電現象の観測
- 2.1.1 沿面放電観測用の電極構成 (模擬複合絶縁系)
- 2.1.2 実験装置と計測方法
- 2.1.3 計測結果と所見
- 2.1 油中沿面放電現象の観測
- 3.絶縁油/油浸プレスボード界面のインパルス沿面放電特性
- 3.1 油中沿面放電現象の観測
- 3.1.1 実験装置と計測方法
- 3.1.2 計測結果と所見
- 3.1 油中沿面放電現象の観測
第7節 封止樹脂の透湿性低減・塩水浸入抑制による封止信頼性向上
- 1.封止接着剤の透湿性低減による封止信頼性向上
- 1.1 水蒸気の透過現象
- 1.2 透湿性の評価方法
- 1.3 エポキシ樹脂系接着剤と透湿性の関係
- 1.3.1 樹脂組成と透湿性の関係
- 1.3.2 無機材料配合量と透湿性の関係
- 1.3.3 樹脂厚みと透湿性の関係
- 2.封止樹脂の塩水浸入抑制による封止信頼性向上
- 2.1 水分浸入挙動と塩水浸入挙動の違い
- 2.2 浸漬・乾燥による塩水浸入挙動
- 2.2.1 浸漬・乾燥1サイクルでの浸入挙動
- 2.2.2 浸漬・乾燥サイクルによる塩水浸入挙動
- 2.2.3 塩水浸入挙動のまとめ
- 2.3 封止部の塩水浸入抑制策
- 2.3.1 封止部の形状コンセプト
第8節 電気接点上で生じるシリコン固形化反応の化学的検討
- 1.有機シリコンによる接触障害現象
- 1.1 不具合発生領域
- 1.2 メカニズム
- 1.3 化学反応見地からの接触障害現象
- 2.評価装置
- 2.1 評価装置
- 2.2 評価サンプル
- 3.評価結果
- 3.1 高濃度有機シリコン環境での評価
- 3.2 接触抵抗への影響
- 3.3 金属表面の状態
第9節 封止材をはじめとする半導体材料への無機イオン捕捉剤配合による配線、電極のトラブル対策
- 1.イオン捕捉剤「IXE」とは
- 2.イオン捕捉剤「IXE」のイオン捕捉効果
- 3.応用例
- 3.1 エポキシ樹脂コンパウンドによるアルミ配線の腐食抑制
- 3.2 銅配線のマイグレーション抑制
第7章 封止材、バリア材の性能および耐久性の測定評価技術
第1節 最近の半導体封止材料の要求特性と評価方法の概要
- 1.半導体の開発動向
- 1.1 軽薄短小化
- 1.2 高速化
- 1.3 低コスト化
- 2.封止材料
- 2.1 要求特性
- 2.2 封止材料の評価方法
- 3.パワーデバイス
- 3.1 パワーデバイスの開発動向
- 3.2 パワーデバイス用封止材料への要求特性
- 3.3 パワーデバイス用封止材料の評価方法
第2節 エポキシ樹脂の流動解析について
- 1.エポキシ樹脂の物性値の変化
- 2.流動解析手法の概要
- 3.エポキシ樹脂用モデル式の概要
- 3.1 反応速度モデル
- 3.1.1 反応率、反応速度の定義
- 3.1.2 反応速度式の例
- 3.1.3 成形プロセスにおける反応の進行
- 3.2 粘度式モデル
- 3.2.1 粘度に影響を及ぼす要因
- 3.3.2 粘度式モデル
- 3.3.3 粘度変化の計算例
- 3.1 反応速度モデル
- 4.解析例
第3節 熱物性値の測定原理と各種試料の熱伝導率・熱拡散率測定について
- 1.非定常面加熱源法について
- 1.1 測定概要
- 1.2 測定原理
- 1.2.1 通常測定
- 1.2.2 その他の解析手法
- 1.3 測定例
- 1.3.1 通常測定
- 1.3.2 異方性測定
- 1.3.3 薄板測定
- 2.熱線比較法について
- 2.1 測定概要
- 2.2 測定原理
- 2.2.1 熱線比較法
- 2.2.2 うす板状試料測定
- 2.3 測定例
- 2.3.1 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) シートの測定
第4節 熱伝導率・熱拡散率の評価方法について
- 1.熱伝導率・熱拡散率の評価方法
- 1.1 定常法
- 1.2 非定常法
- 1.2.1 パルス加熱法
- 1.2.2 周期加熱法
- 1.2.3 熱拡散率・熱伝導率の分布評価法
- 1.3 測定結果の妥当性
- 2.放熱材料の測定例
第5節 熱応力・熱変形の基礎と解析手法
- 1.熱応力の発生原因
- 2.棒に生じる熱応力
- 2.1 一様断面棒
- 2.2 変断面棒
- 3.はりの曲げによる熱応力
- 3.1 2層積層複合はりの熱応力
- 4.円筒の熱応力
- 5.球の熱応力
第6節 ナノ構造材料における界面熱抵抗の予測
- 1.界面熱抵抗 (thermal resistance) の定義
- 2.界面での熱輸送経路
- 2.1 弾性的なフォノン散乱
- 2.2 非弾性的なフォノン散乱
- 2.3 電子—フォノンカップリング
- 3.界面熱抵抗に影響する材料要因
- 3.1 界面熱抵抗の実験データ
- 3.2 界面ナノ構造と化学結合の影響
- 3.3 結晶性の影響
- 4.界面熱抵抗の予測
- 4.1 Diffusion Mismatch Model
- 4.2 データ駆動モデル
第7節 パルスNMR法によるエポキシ樹脂の硬化過程に関する分子運動論的検討
- 1.原理
- 2.試料
- 3.装置
- 4.実験結果
- 4.1 自由誘導減衰信号の変化と解析
- 4.2 スピン-スピン緩和時間とその分率の反応時間依存性
- 4.3 スピン-格子緩和時間の反応時間依存性
- 4.4 硬化後の熱的挙動
第8節 実践 バリアフイルム・封止材・容器のガスバリア性評価の方法
〜等圧法における さまざまなサンプルの測定方法〜
- 1 フイルムの測定
- 1.1 小さなサンプルや低バリアフイルムの測定
- 1.2 薄いサンプルと厚いサンプルの測定
- 1.3 表面に凹凸があるサンプルの測定
- 1.4 多層化されたサンプルの測定
- 1.4.1 シリカSiOx蒸着フイルムの水蒸気透過度測定
- 1.4.2 アルミ蒸着フイルムの水蒸気透過度測定
- 1.4.3 多層品のテストガス透過方向性と測定結果
- 1.4.4 湿度依存性のあるサンプル測定
- 1.4.5 エポキシ樹脂接着剤の測定
- 1.4.6 高温高湿での測定
- 2 容器 (パッケージ) の測定
- 2.1 容器と試験治具
- 2.2 PETボトルの酸素透過率測定 (以下O2TRと略す)
- 2.3 歯磨き粉チューブ・プラスチック容器・目薬容器のO2TR
- 2.4 紙パック (ジュース、酒) ・菓子袋のO2TR
- 2.5 ハードコンタクトレンズのO2TR
- 2.6 様々な容器のO2TR
- 2.7 PTP (Push Trough Pack) の水蒸気透過度の測定 (WVTRと略す)
- 2.8 PTP 太陽光発電パネルのWVTR
- 2.9 炭酸飲料PETボトルの測定
- 2.10 密閉された容器のWVTR
- 3 ガスバリア性試験装置の測定原理 (等圧法)
- 3.1 酸素透過率試験装置 (クーロックス法 反応電気量を測定)
- 3.2 水蒸気透過度試験装置 (赤外線法 赤外線吸収量を測定)
- 3.3 超高感度水蒸気透過度試験装置 (クーロメトリック法 反応電気量を測定)
- 4 ガスバリア性試験装置の較正方法
- 5 ガスバリア性試験装置の性能仕様
- 6.等圧法におけるP・D・S係数
第9節 バリアフィルム・封止材のガスバリア性評価ガスクロマトグラフ法
- 1.関連規格
- 1.1 JIS K7126:プラスチック-フィルム及びシート-ガス透過度試験方法
- 1.2 JIS K7129:プラスチック-フィルム及びシート-水蒸気透過度の求め方
- 2.測定方法
- 2.1 差圧式ガスクロマトグラフ法
- 2.1.1 ガスクロマトグラフ法の特長
- 2.1.2 差圧式外観構成と流路図
- 2.1.3 GTR-1000XA仕様
- 2.1.4 分析実用例
- 2.1.5 分析実用例
- 2.1 差圧式ガスクロマトグラフ法
第10節 バリア材料の水蒸気透過度測定について
- 1.代表的な水蒸気透過度測定の原理について
- 2.10-6乗領域の検出が可能な高感度水蒸気透過度測定法について
第11節 太陽電池モジュール材料の紫外線照射による劣化評価
- 1.UV-Py/GC-MSシステムによる揮発性劣化生成物の分析
- 1.1 概要
- 1.2 分析結果
- 2.フーリエ変換赤外分光光度計 (FTIR) によるUV照射EVAの分析
- 2.1 概要
- 2.2 分析結果
第8章 半導体および電気電子機器における封止・バリア技術
第1節 パワーデバイス向け樹脂封止材料の高耐熱・高絶縁設計技術
- 1.パワーデバイスの用途
- 2.パワーデバイスの技術動向
- 3.高耐熱高絶縁性樹脂の設計
- 4.封止樹脂の今後の技術展望
第2節 三次元実装プロセスへの機能性粘着フィルムの応用の可能性
- 1.粘着フィルムの構成
- 2.粘着フィルム起因の被着体汚染
- 2.1 被着体の汚染
- 2.2 粘着剤起因による汚染
- 2.3 基材フィルム起因による汚染
- 2.4 セパレータ起因による汚染
- 3.粘着剤設計から見た剥離力低減を抑えるための対策
- 4.半導体ウェハ加工対応プロセス材料
- 4.1 ウェハグラインディング
- 4.2 ウェハダイシング
- 4.3 新規アプリケーション/新規プロセス材料の提案
第3節 FOWLP向け仮貼り合わせ、剥離技術
- 1.FOWLP向け仮貼り合わせ/剥離方式
- 1.1 機械式剥離
- 1.2 レーザー剥離
- 2.パネルレベルへの対応
第4節 MEMSのウェハレベルパッケージング
- 1.慣性センサーのWLP
- 2.陽極接合を利用したWLP
- 3.ASICとMEMSのウェハレベル集積化
- 4.BAWフィルタのWLP
- 5.圧力センサーのWLP
第5節 エポキシ系封止材料や接着剤による自動車部材の防振・制振、耐衝撃性技術
- 1.防振・制振
- 2.耐衝撃性
第6節 振動吸収・高耐熱性ウレタンゲル封止材料における自動車用電子機器などへの応用
- 1.電気絶縁用のウレタン樹脂の原料
- 1.1 ポリオール
- 1.1.1 ひまし油系
- 1.1.2 ポリブタジエン系
- 1.1.3 ポリオレフィン系
- 1.2 イソシアネート
- 1.2.1 MDI, TDI系 (芳香族系)
- 1.2.2 XDI系 (芳香族系)
- 1.2.3 H-MDI, H-XDI系 (脂環式系)
- 1.2.4 IPDI, NBDI系 (脂環式系)
- 1.2.5 HDI系 (脂肪族系)
- 1.3 鎖延長剤
- 1.4 触媒
- 1.5 耐候剤
- 1.6 その他
- 1.6.1 可塑剤
- 1.6.2 消泡剤
- 1.6.3 レベリング剤
- 1.6.4 フィラー類
- 1.6.5 抗菌剤
- 1.6.6 密着付与剤
- 1.6.7 難燃剤
- 1.1 ポリオール
- 2.注型技術
- 2.1 手作業による注型
- 2.2ディスペンサーによる定量吐出
- 3.ウレタン樹脂の劣化
- 3.1 ウレタン結合の劣化
- 3.2 エーテル結合の劣化
- 3.3 不飽和結合の劣化
- 4.ウレタンゲルの構造
- 4.1 柔軟系ウレタン
- 4.2 従来のウレタンゲル
- 5.配合技術と特性
- 5.1 一般ゲルタイプ
- 5.2 高耐湿熱タイプ
- 5.3 高耐熱、高耐湿熱タイプ
- 5.4 硬度可変タイプ
- 6.更なる高機能化
- 6.1 熱伝導タイプ
- 6.2 特殊接着タイプ
- 6.3 難燃タイプ
- 7.ウレタン樹脂としての新たな展開
第7節 宇宙用超低アウトガスシリコーンの特性と評価
- 1.NASAの低アウトガス及び超低アウトガス試験及び評価基準
- 2.試験対象材料
- 3.試験方法
- 4.ASTM試験結果
- 4.1 ASTM E5959
- 4.2 ASTM E155910
第9章 ディスプレイ、照明、光学分野における封止・バリア技術
第1節 次世代ディスプレイの展望と封止関連技術
- 1.Society 5.0および第5世代移動通信システム (5G) とディスプレイデバイス
- 1.1 Society 5.0と第5世代移動通信システム (5G)
- 1.2 全世界のトラフィックの予測
- 1.3 人間の五感とディスプレイ (2)
- 1.4 ディスプレイデバイスの定義 (2)
- 1.5 ディスプレイの評価要素
- 1.5.1 空間解像度 (spatial resolution)
- 1.5.2 時間解像度 (temporal resolution)
- 1.5.3 コントラスト (contrast)
- 1.5.4 色再現範囲 (color gamut)
- 1.5.5 量子化率 (quantization)
- 1.6 ディスプレイデバイスの比較
- 2.液晶TV用TFT-LCD
- 2.1 アダプティブ・ディミング (adaptive dimming)
- 3.OLED TV用OLEDディスプレイ
- 4.高精細・高フレームレートFPDに欠かせないIGZO-TFT
- 4.1 表示容量とTFT特性
- 4.2 LTPSのオン電流と同等の高品質IGZO-TFT
- 4.3 30インチ4KローラブルOLEDディスプレイ
- 5.バリア膜、封止材料
- 5.1 バリア膜、封止材料への要求事項
- 5.2 OLEDデバイス用高透明粘着封止フィルム
第2節 高信頼性ディスプレイを実現する封止技術
- 1.有機ELディスプレイ
- 1.1 有機ELの劣化メカニズム
- 1.2 有機ELに求められる封止性能と評価法
- 1.3 レーザーガラス封止
- 2.量子ドットディスプレイ
第3節 ナノコンポジットによるポリマーの透明化と光学特性制御
- 1.透明性維持のための必要条件
- 2.ナノコンポジット材料の合成
- 2.1 ナノ粒子合成
- 2.2 ゾル-ゲル溶液反応の適用
- 2.3 熱硬化・光硬化反応の適用
- 2.4 熱可塑性ナノコンポジット材料
- 3.ナノコンポジット材料の光学特性
- 3.1 ナノコンポジット化による屈折率制御
- 3.2 熱膨張率・屈折率温度依存性の制御
第4節 エポキシ封止材 における LEDやディスプレイなどへの応用
- 1.LED封止材の要求特性
- 2.LED封止材の変遷
- 3.脂環式エポキシ樹脂の取り組み
- 4.エポキシ樹脂封止材の高機能化の取り組みと性能評価
- 5.ディスプレイ向けコーティング材料
第5節 フレキシブル対応の新規バリア技術の開発とその可能性について
- 1.フレキシブル基板における現在のガスバリア技術
- 2.ロールtoロール法を用いた新規な単層無機バリア膜
- 3.スパッタ法とALD法を用いた高耐熱EXPEEKバリアフィルム
第6節 フレキシブル対応の新規封止技術の開発とその可能性について
- 1.リジッド有機ELの現行の封止技術
- 2.フレキシブル有機ELの現行の封止技術
- 3.新規な有機樹脂材料を用いた無機/有機/無機交互積層膜
- 4. ラミネート方式を用いたフレキシブル有機ELデバイスの開発
第7節 有機EL用封止材料の要求特性と封止技術
- 1.中空封止構造向けの端面封止材について
- 2.有機EL用封止材料のフレキシブル化への対応
- 2.1 ダム&フィル封止
- 2.2 液状材料を用いた全面封止
- 2.3 感圧接着剤 (PSA) を用いた封止
- 2.4 薄膜封止
第8節 フォルダブルディスプレイ市場の動きと封止技術等の動向
- 1 有機ELディスプレイの概略構造と基本技術
- 1.1 封着技術
- 1.2 タッチパネルを含めた基板材料/カバー材料
- 2.UTGの化学強化の方向性
- 3.フォルダブルディスプレイに対応した化学強化ガラス
- 4.フォルダブルディスプレイの方向性と総括
第9節 病理検査に使用するプレパラート用ガラスと各種切片との接着メカニズム
- 1.プレパラート作成のための工程
- 2.プレパラート用ガラスと各種切片との接着・密着性、必要とされる表面処理
- 3.ガラスと細胞組織との密着性を良くする方法の学問的な裏付け
- 4.バイオチップ商品とシランカップリング剤の付加技術
- 5.プレパラート用材料の市場と将来展開
第10章 蓄電池、エネルギー分野における封止・バリア・シーリング技術
第1節 アイオノマー太陽電池封止材
- 1.封止材用樹脂に求められる性能と弊社の取り組みについて
- 2.アイオノマー樹脂「ハイミラン?」について
- 2.1 アイオノマー封止材の特徴について
- 2.1.1 柔軟性
- 2.1.2 接着性
- 2.1.3 透明性
- 2.1.4 水蒸気透過性
- 2.1.5 電気絶縁性
- 2.1.6 耐熱性
- 2.6.7 耐久性
- 2.6.8 ラミネート適性
- 2.1 アイオノマー封止材の特徴について
第2節 封止材の長期信頼性とモジュールへの影響
- 1.封止材の開発目標
- 2.EVAの信頼性試験結果
- 3.封止材の今後の方向性と課題
第2節 色素増感太陽電池用の封止材料と技術
- 1.DSSCの発電の原理とその構成
- 2.DSSCの作製過程と封止方法
- 3.DSSC用の封止剤の現状
第3節 リチウムイオン電池の封止技術と評価
- 1.リチウムイオン電池の基本構成と内部構造
- 1.1 リチウムイオン電池の特徴と構成
- 1.2 裸セルの材料、部材の構成 体積%
- 1.3 液系セルにおける電解質溶液
- 1.2 Mの分布
- 1.4 セルの電極構造と熱伝導 (放熱)
- 1.5 温度とリチウムイオン電池 (セル) の挙動
- 1.6 揮発成分としての有機電解液の融点と沸点
- 1.7 有機電解液の引火点と消防法規制
- 1.8 過放電セルのガス分析 水素、可燃性炭化水素ほか
- 2.電池の外装型式、封止方法と電極端子
- 2.1 電池の構造と封止技術
- 2.2 リチウムイオン電池の製造全工程
- 2.3 電池 (セル) の外装型式と電極板製造
- 2.4 大形リチウムイオン電池の外装型式と特性 (1)
- 2.5 大形リチウムイオン電池の外装型式と特性 (2)
- 2.6 円筒型電池の構造と封止、短絡事故例
- 2.7 円筒型26φ650mmセルの封止と排気弁
- 2.8 ラミネート型と角槽型、ガス対策
- 2.9 新規な外造構造、東芝SCiBセル
- 2.10 ラミネートの真空シーラーと電解液充填機
- 2.11 ラミネート包材におけるタブの封止
- 2.12 シーラントタブ封止部の引張り強度
- 2.13 シーラントタブ封止部引張り強度
- 2.14 ラミネート型セルの端子と放熱 (放電) 性
- 2.15 直列ラミネートセルのガス膨張 (過放電)
- 2.16 三直列セルの過充電 (ガス膨張)
- 2.17 角槽型電池の端子構造例
- 2.18 円筒電池の電解液漏れ試験、特許出願
- 3. EV電池システムの冷却方法と封止の関連
- 3.1 セルの形状と冷却方式 (HV,PHVとEV)
- 3.2 EV電池ユニットの冷却方式
- 3.3 GSyuasa角槽セルと冷却方法
- 3.4 角槽型セルの液冷システム (AUDI社)
- 3.5 円筒型セルの液体循環冷却 (TESLA社)
- 4. 封止技術と安全性試験規格 (UN,UNECE/R100)
- 4.1 UL2580の試験項目 (2)
- 4.2 中国のGB/T 31467.3-2015
- 4.3 UNの安全性試験 (T1-T4) (PartIII.38,3)
- 4.4 UNの安全性試験項目 (T5-T8) (PartIII.38,3)
- 4.5 EVの発火事故とリコール,2020/10
第4節 液漏れを防止する高耐久リチウムイオン電池 (カシメ部) 用シール材
- 1.シール材とは
- 2.シール材の要求特性
- 3.シール材の塗布方法
- 4.シール材に使われる材料
- 4.1 材料選定のポイント
- 4.2 アスファルト系シール剤
- 4.3 ゴム系シール剤
- 5. アスファルト系シール材とゴム系シール材の比較
- 6.シール材の技術課題とこれからのシール材
第5節 バリア性粘土膜プラスチック複合材の高圧水素ガスタンクへの応用
- 1.ガスバリアフィルムの開発動向
- 2.水素ガスバリア性粘土膜の開発
- 2.1 粘土膜とそのガスバリア性
- 2.2 加熱耐水化粘土の使用による加湿環境下での水素バリア性
- 2.3 粘土膜CFRP複合材料の開発
- 2.4 水素ガスタンクの試作
第6節 高圧水素ガスバリア材の開発と燃料電池用水素ガスタンクへの応用
- 1.高圧水素曝露下で引き起こされる高分子材料の課題と対策
- 1.1 ブリスタ破壊
- 1.2 コラプス破壊
- 1.3 低温〜高温域の力学特性の最適化
- 1.4 その他 (環境応力破壊)
- 2.各種高分子材料について
- 3.水素耐性付与に関わる検討例
- 3.1 ポリビニルアルコール系樹脂と酸無水物変性テトラフルオロエチレン (融点176°C、以下ETFE) からなるポリマーアロイ
- 3.2 BVD4E16と超低密度ポリエチレンからなるポリマーアロイ
- 3.3 ポリアミド6-66とBVD4E16からなるポリマーアロイ
- 3.4 高圧水素急減圧に伴うポリエチレンのボイド形成:放射線架橋による抑制
- 3.5 高密度ポリエチレン及びPA6-66 (=50wt%/50wt%) からなるポリマーアロイのグラフェンによる改質効果
第7節 EVOH樹脂の燃料システムへの応用とバイオ燃料への対応
- 1.EVOH樹脂の燃料システムへの応用
- 2.バイオ燃料への対応
第8節 POM樹脂の燃料系部品への応用と市場環境への対応
- 1.燃料系部品にPOM樹脂が選択される理由
- 1.1 機械的性質
- 1.2 耐燃料性
- 1.3 締結性
- 2.POM樹脂が使用されている燃料系部品
- 2.1 フューエルセンダーモジュール
- 2.2 モジュール固定用ナット
- 2.3 キャップ
- 2.4 バルブ類
- 3.燃料系部品向けのPOM樹脂の開発動向
- 3.1 高流動・高剛性
- 3.2 耐燃料性 (硫黄含有燃料)
- 3.3 耐酸性
- 3.4 導電性
第11章 封止・バリア・シーリング技術に関する特許動向
第1節 封止に関する特許動向
第2節 積層体バリア技術に関する特許動向
第3節 シーリング技術に関する特許動向
出版社
お支払い方法、返品の可否は、必ず注文前にご確認をお願いいたします。
体裁・ページ数
A4判 689ページ
ISBNコード
978-4-86798-124-5
発行年月
2021年4月
販売元
tech-seminar.jp
価格
63,000円 (税別) / 69,300円 (税込)
これから開催される関連セミナー
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 半導体封止材の設計・開発とその技術および半導体パッケージのトレンド | オンライン | |
| 2025/11/17 | 半導体封止材の設計・開発とその技術および半導体パッケージのトレンド | オンライン | |
| 2025/11/21 | 半導体の製造プロセスと半導体用材料の基礎入門 | オンライン | |
| 2025/11/25 | 半導体の製造プロセスと半導体用材料の基礎入門 | オンライン | |
| 2025/11/27 | ヒートシールの基礎、接合のメカニズムと品質管理・不具合対策 | オンライン | |
| 2025/12/9 | カーボンナノチューブの分散・加工技術と応用研究の動向 | オンライン | |
| 2025/12/11 | 薄膜の剥離メカニズムと密着性の評価、改善手法 | オンライン | |
| 2025/12/11 | ヒートシールの基礎、接合のメカニズムと品質管理・不具合対策 | オンライン | |
| 2025/12/12 | ガスバリア技術の基礎と活用動向およびウェットプロセスによるウルトラ・ハイバリア技術 | オンライン | |
| 2025/12/18 | カーボンナノチューブの分散・加工技術と応用研究の動向 | オンライン | |
| 2026/1/21 | フィルム製造における製膜/成形技術とスリット・巻取り技術の基礎と実際 | オンライン | |
| 2026/2/5 | フィルム製造における製膜/成形技術とスリット・巻取り技術の基礎と実際 | オンライン |
関連する出版物
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2024/8/30 | 次世代パワーデバイスに向けた高耐熱・高放熱材料の開発と熱対策 |
| 2023/9/29 | 先端半導体製造プロセスの最新動向と微細化技術 |
| 2018/10/1 | 軸受の密封 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
| 2018/9/27 | プラズマCVDにおける成膜条件の最適化に向けた反応機構の理解とプロセス制御・成膜事例 |
| 2014/4/5 | 真空蒸着技術 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
| 2014/4/5 | 真空蒸着技術 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2012/1/30 | 水処理膜の製膜技術と材料評価 |
| 2010/3/1 | シリコーン製品市場の徹底分析 |
| 2010/2/25 | コーティング材料のコントロールと添加剤の活用 |
| 1990/9/1 | LSI樹脂封止材料・技術 |
| 1990/6/1 | LSI周辺金属材料・技術 |