技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
タンパク質、細胞の吸着制御技術
タンパク質、細胞の吸着制御技術
~医療用包材、医薬品容器、培養基材、医療機器、医療材料、膜/フィルター~
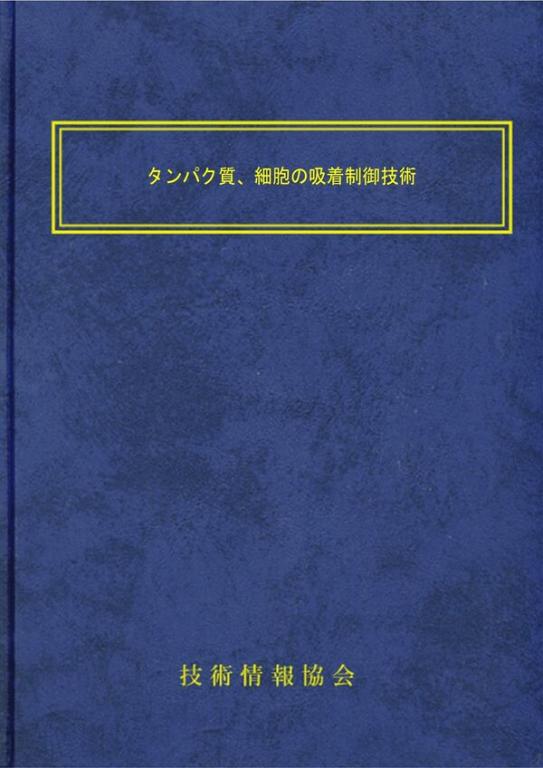
ご案内
- 高分子、無機材料、金属表面へのタンパク質吸着、細胞接着のメカニズム
- 高分子バイオマテリアルの水分子の動的挙動
- タンパク質のステンレス鋼表面に対する付着挙動
- 病原微生物の付着と定着のメカニズム
- グラフェン上へのタンパク質・アミノ酸吸着特性の電気的評価
- タンパク質、細胞、細菌の吸着を抑制するコーティング、表面改質技術
- 低吸着樹脂の製品開発と材料表面の付着性評価
- 吸着したタンパク質を除去するゲル表面の構築
- 星型ポリマーコーティングによるタンパク質、細胞の付着抑制
- 親水性ポリマーブラシの調製と医療への応用
- タンパク質の吸着・脱離を制御できる温度応答性材料
- MPCポリマーの特性と生体適合性ポリマーとしての可能性
- ポリウレタンチューブのDLCコーティングによる細菌付着抑制
- 銅含有DLC膜による抗菌性メカニカルコーティングの開発
- タンパク質、細胞の吸着を促進させる表面処理技術と材料の開発
- 細胞培養基材の設計ポイント
- タンパク質吸着のためのバイオセラミック粒子の表面機能化
- 細胞接着を光制御できる機能性基板
- 光の局所照射による細胞の接着領域制御
- セラックへの細胞接着性の付与
- タンパク質 吸着量の評価
- タンパク質の吸着量と凝集体の関係性
- 吸着タンパク質の定量評価
- 接触角によるタンパク質吸着量の評価
- 蛍光顕微鏡を用いた吸着の直接評価
- X線光電子分光 (XPS) によるタンパク質吸着性評価
- 金属バイオマテリアル表面でのタンパク質吸着と細胞接着
- 医療用容器、抗血栓、抗菌、抗バイオフィルム材料への応用
- コーティング材料の抗血栓性作用機序
- ポリエチレン (PE) の改質による抗血栓性化
- コラーゲンの立体構造修飾による脱細胞組織の抗血性化
- 抗血栓性ポリマーの脱細胞化肝臓足場への活用
- 合成系コーティング材料の医療機器への応用
目次
第1章 材料表面へのタンパク質,細胞低吸着性を付与する表面処理技術
1節 DLC の分類と細胞接着性評価
- はじめに
- 1.DLCの物性
- 1.1 光学定数
- 1.2 DLCの表面状態
- 2.DLCの細胞評価
- 2.1 細胞接着性評価
- 2.2 細胞接着性と表面状態
- 3.まとめ
2節 ePTFE基材へのDLC成膜による血液適合性向上
- はじめに
- 1.ePTFE製人工血管について
- 1.1 人工血管の現状
- 1.2 問題点と既存改変技術
- 1.3 人工血管に求められる表面特性とは?
- 2.DLC成膜による血液適合性評価 (in vitro試験)
- 2.1 表面性状評価 (物理化学的変化)
- 2.2 タンパク・血小板付着試験
- 2.3 ヒト全血接触試験
- 3.DLC成膜による血液適合性変化 (in vivo試験)
- 3.1 ラット全血接触試験 (循環中での生体環境内)
- 3.2 ラット腹部大動脈置換
- 3.3 ブタ頚動脈・静脈置換 (超急性期での観察)
- 3.4 ヤギ頚部動静脈シャント (長期での観察)
- 4.おわりに (DLC人工血管の将来展望)
3節 ポリウレタンチューブのDLCコーティングによる細菌付着抑制
- はじめに
- 1.ポリウレタンに対するDLCコーティングの評価
- 1.1 Diamond-like carbon (DLC) コーティング技術
- 1.2 ポリウレタンに対するDLCコーティングのin vitroでの評価
- 2.ポリウレタンチューブに対するDLCコーティングでの細菌付着
- 2.1 細菌液との接触方法
- 2.2 静置試験
- 2.3 灌流試験
- 2.4 細菌とBiofilmの評価
- 3.結果
4節 銅含有DLC膜による抗菌性メカニカルコーティングの開発
- はじめに
- 1.作製方法
- 2.構造評価
- 2.1 表面観察
- 2.2 元素分析
- 3.機械特性評価
- 4.抗菌抗ウイルス性評価
- おわりに
5節 ホスホリルコリン修飾によるグラフェン表面のタンパク質吸着抑制
- はじめに
- 1.4H-SiC基板上エピタキシャルグラフェンの合成
- 2.実験手法
- 2.1 ピレン基とホスホリルコリン分子の合成
- 2.2 接触角と電気特性評価
- 3.実験結果と考察
- 3.1 ホスホリルコリン修飾による接触角・抵抗率変化
- 3.2 タンパク質吸着抑制
第2章 タンパク質の吸着を抑制する生体適合性ポリマーの開発、表面改質技術
1節 生体親和性を指向した機能性重合材料
- はじめに
- 1.親水性多官能モノマーの基本特性
- 1.1 硬化性
- 1.2 溶解性
- 1.3 安定性 (耐加水分解性)
- 1.4 安全性 (生物学的安全性)
- 2.架橋ポリマーとした場合の基本特性
- 3.生体親和性材料として応用した実例
- 3.1 抗血栓性
- 3.2 血漿タンパク質吸着性
- 3.3 がん細胞接着性 なぜ抗血栓性のがん細胞接着性材料が必要なのか?
- おわりに
2節 GLMA系生体適合性ポリマーのタンパク質吸着性
- はじめに
- 1.中間水と細胞接着
- 2.中間水が少ないGLMA (グリセリンモノアクリレート) 系ポリマー
- 3.中間水が多いGLMA系ポリマー
- 4.GLMA系ポリマーの生物接着
- 5.GLMA系ハイドロゲル
- 6.おわりに
3節 シクロオレフィンポリマー (COP) のタンパク質吸着性、凝集体について
- はじめに
- 1.環状オレフィンポリマー (COP)
- 1.1 COPの原料について
- 1.2 COPの合成方法について
- 2.医療用包装材料としてのCOP
- 2.1 透明性
- 2.2 強度
- 2.3 低温特性
- 2.4 不純物
- 2.5 各種滅菌方法への適合性
- 3.COP製シリンジ中のタンパク質の吸着性、凝集性
- 3.1 シリンジへのタンパク製剤の吸着性について
- 3.2 シリンジ中のタンパク製剤の凝集体発生について
4節 低吸着樹脂の製品開発と材料表面の付着性評価
- はじめに
- 1.従来のディスポーザブル樹脂製品と求められる製品
- 1.1 規格サイズの統一
- 1.2 低吸着の定義
- 1.3 低吸着樹脂製品
- 2.シロキサン含有樹脂製品の基本設計
- 2.1 シリコーンが剥離しない樹脂製品
- 2.2 製造上の解決すべき課題点
- 3.低吸着の簡便評価法
- 3.1 従来の吸着評価法
- 3.2 蛍光顕微鏡を用いた吸着の直接評価
- 4.成型品の評価
- 4.1 平板成型品の吸着評価
- 4.2 成型条件の最適化
- 4.3 局面部位の吸着評価
- 5.DNAとタンパク質吸着の比較
- 5.1 ベース樹脂による吸着の比較
- 5.2 タンパク質を低吸着にする樹脂
- 6.液切れ評価
- 7.細胞培養の評価と製品評価
- 7.1 シロキサン含有樹脂シャーレを用いた細胞培養
- 7.2 シリコーン部の溶出評価
- 7.3 電子線滅菌によるシロキサン含有樹脂の影響
- おわりに
5節 合成系コーティング材料「セックワン」の医療機器への応用
- はじめに
- 1.セックワン?とは
- 1.1 セックワンの特徴
- 1.2 セックワンの親水性基の特徴
- 1.3 セックワンの疎水性基の特徴
- 1.4 セックワンの撥水性の特徴
- 2.セックワン?による抗血栓性作用機序
- 2.1 血栓形成カスケード
- 2.2 ヘパリンの効果
- 2.3 ウロキナーゼの効果
- 2.4 セックワン?の抗血栓性効果の考察
- おわりに
6節 親水性ポリマーブラシの潤滑性と医療材料への応用
- はじめに
- 1.ポリマーブラシによる表面の親水化
- 2.親水性ポリマーブラシによる水中潤滑機構
- 3.親水性ポリマーブラシの調製と医療への応用
- おわりに
7節 タンパク質吸着抑制能を有する分解性ハイドロゲル表面の構築
- はじめに
- 1.水中で表面近傍からの分解を生じるハイドロゲル
- 1.1 分解性温度応答性ハイドロゲル
- 1.2 分解性温度応答性ハイドロゲルの合成と物性解析
- 2. 表面近傍の分解により吸着したタンパク質を除去するゲル表面の構築
- 2.1 Poly (ethylene glycol) グラフト鎖の再露出
- 2.2 ゲル表面からの吸着したタンパク質の除去
- 3.今後の展望
8節 星型ポリマーコーティングによるタンパク質、細胞の付着抑制
- はじめに
- 1.星型ポリマーの製造および表面コーティング
- 1.1 基材表面に対するポリマーのグラフト方法
- 1.2 ポリマーグラフト表面代替としての星型ポリマー
- 2.星型ポリマーコーティングによるタンパク質吸着抑制
- 2.1 星型ポリマーコーティング表面に対するタンパク質吸着量
- 2.2 星型ポリマーコーティング表面の電気的性質
- 3.星型ポリマーコーティングによる細胞付着抑制
- おわりに
9節 タンパク質の吸着・脱離を制御できる温度応答型水圏機能材料
- はじめに
- 1.温度応答性高分子と温度応答性クロマトグラフィー
- 1.1 温度応答性クロマトグラフィー
- 1.2 温度応答性高分子修飾クロマトグラフィー担体の作製方法
- 1.3 疎水性相互作用を強力にした温度応答性クロマトグラフィー
- 1.4 温度応答性イオン交換クロマトグラフィー
- 2.タンパク質分離のための温度応答性高分子を用いた分離材料
- 2.1 荷電性官能基を有する温度応答性高分子を用いたタンパク質分離用材料
- 2.2 タンパク質との特異的な相互作用を利用した温度応答型タンパク質分離精製材料
- 3.治療用細胞精製のための温度応答性高分子を用いた分離材料
- 3.1 温度応答性高分子を修飾したガラス基板による細胞分離
- 3.2 細胞との生物的親和性を利用した細胞分離
- 3.3 大容量細胞分離を実現する温度応答性マイクロファイバーと細胞分離カラム
- 4.次世代医薬品精製のための温度応答性高分子を用いた分離材料
- 4.1 ウイルスベクターの分離精製
- 4.2 細胞外小胞の分離精製
- 結言
10節 タンパク質吸着防止ポリマーの開発とタンパク質安定化効果
- はじめに
- 1.BlockmasterTMの設計コンセプト
- 2.BlockmasterTMのタンパク質吸着防止性能
- 2.1 DB1130のタンパク質吸着防止性能及び体外診断薬への応用
- 2.2 PA1080によるプレート、メンブレンへのブロッキング効果及び細胞接着防止効果
- 3.BlockmasterTMのタンパク質安定化効果
- 3.1 BlockmasterTMのタンパク質安定化メカニズム
- 3.2 異なる材質の容器に対するBlockmasterTMのタンパク質 (前立腺特異抗原PSA) 安定化効果
- 3.3 凍結融解工程におけるBlockmasterTMのタンパク質 (ペプシノーゲン (I) , (II) ) 安定化効果
- おわりに
11節 低タンパク質吸着性、血液適合性を持つ医療用コンパウンド
- 1.医療現場で必要とされるプラスチック製品
- 1.1 三菱ケミカルの医療ソリューション
- 1.2 医療用コンパウンド Zelas?
- 1.3 低タンパク質吸着医療コンパウンドの可能性
- 1.4 タンパク質吸着の評価方法
- 2.両親媒性ポリマー含有コンパウンド ZelasTM AMP
- 2.1 開発背景
- 2.2 μBCA法によるタンパク質の吸着量の評価
- 2.3 ZelasTM AMP-Key polymer
- 2.4 軟質ポリ塩化ビニル (軟質PVC) へのZelas?AMP-Key polymerの改質効果
- 2.5 医療用ポリウレタンへのZelas? AMP-Key polymerの改質効果
- 3.非晶性オレフィン Zelas? CPの開発
- 3.1 開発の背景
- 3.2 医薬品包装への展開
- 3.3 検査診断機器/理化学消耗品への展開
- 4.医療用素材の事業環境と今後の展開
12節 MPCポリマーコーティングによる義歯用レジンへのカンジダ付着抑制効果
- はじめに
- 1.MPC-polymerおよびアクリル義歯用樹脂プレート (acrylic denture resin plates: ADRP) の調整と特性
- 1.1 ADRPの親水・疎水性への影響 (接触角の測定)
- 2.MPC-polymerのCandida増殖に対する影響
- 3.MPC-polymerがCandidaのアクリル義歯用樹脂プレート (ADRP) への付着に及ぼす影響
- 4.MPC-polymer処理ADRPへのCandidaの付着とCandida表面の疎水性との相関関係
- おわりに
13節 MPCポリマーの特性と生体適合性ポリマーとしての可能性
- はじめに
- 1.MPCポリマーの特性
- 1.1 MPC (2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン) とは
- 1.2 MPCポリマー
- 1.3 MPCポリマーの機能と生体適合性
- 1.3.1 生体適合性とは
- 1.3.2 MPCポリマーの機能
- 1.4 MPCポリマーの用途
- 1.4.1 アイケア分野
- 1.4.2 医療用デバイス・組織培養分野
- 1.4.3 診断薬分野
- おわりに
14節 タンパク質の吸着や細胞の付着を防ぐ表面コーティング材料設計
- はじめに
- 1.コーティング材料 (Chol-U-Pr-mPEG) の水溶液物性評価
- 2.コーティングされたPP表面の特性
- 3.タンパク質の吸着抑制
- 4.血小板の付着抑制
- 5.おわりに
15節 病原微生物の付着と定着のメカニズムと付着・定着を抑制する成分の検索
- はじめに
- 1.食品成分からのバイオフィルム阻害剤の検索
- 1.1 茶カテキンによるバイオフィルム阻害
- 1.2 キノコ抽出物によるバイオフィルム阻害
- 2.AIの不活化によるバイオフィルムの制御
- 2.1 E. corrodensにおけるAI-2の不活化によるバイオフィルムの制御
- 3.細菌が生産するバイオフィルム阻害剤
- 3.1 植物内生放線菌からのバイオフィルム阻害剤の検索
- 3.2 南極で分離した細菌からのバイオフィルム阻害剤の検索
16節 小麦粉由来アラビノキシランの大腸菌付着抑制効果
- はじめに
- 1.大腸菌の非生物素材への付着に対する穀類抽出液の影響
- 2.小麦粉由来付着抑制物資の精製と性質
- 3.種々の細菌の非生物素材への付着に対するアラビノキシランの抑制活性
- 3.1 種々の細菌の非生物素材への付着に対するアラビノキシランの抑制活性
- 3.2 腸管出血性大腸菌O157の付着に対する市販多糖類の影響
- 4.種々の非生物素材への大腸菌の付着に対するアラビノキシランの抑制効果
- 5.アラビノキシランによる素材表面の物性変化
- 6.素材表面に付着したアラビノキシランの洗浄方法
- 終わりに
17節 テオブロミンおよびS-PRGフィラー含有歯面コーティング材の細菌付着抑制効果
- はじめに
- 1.歯面コーティングの開発
- 1.1 テオブロミンとは
- 1.2 S-PRGフィラーとは
- 1.3 テオブロミンおよびS-PRGフィラー含有歯面コーティング材
- 2.まとめ
第3章 タンパク質の吸着特性とその評価
1節 QCMによるタンパク質吸着の測定
- はじめに
- 1.QCMの原理
- 2.QCM測定から得られる測定量
- 2.1 基本的な測定量
- 2.2 QCMの様々な拡張モードについて
- 3.タンパク質吸着の測定事例
- 3.1 QCMを用いたタンパク質の吸着
- 3.2 QCM-Dを使った、膜の解析とタンパク質の吸着の解析
2節 タンパク質の吸着量と凝集体の関係性と吸着タンパク質の定量評価
- 1.タンパク質の吸着量と凝集体
- 2.吸着したタンパク質の定量方法
- 2.1 吸着量を間接的に定量する方法
- 2.2 吸着量を直接的に定量する方法
- 2.2.1 吸着層を剥離して定量する方法
- 2.2.2 放射性同位体元素 (radioisotope: RI) 標識による定量
- 2.2.3 界面に特異的な方法
- 2.2.4 エリプソメトリー
- 2.2.5 原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscopy: AFM)
- 2.2.6 水晶振動子マイクロバランス法 (Quarts Crystal Micobalance: QCM)
- 2.2.7 表面共鳴プラズモン (Surface Plasmon Resonance: SPR)
3節 高分子バイオマテリアルの水分子の動的挙動
- はじめに
- 1.高分子の分子量による分子運動性と低温結晶化挙動
- 1.1 生体適合性高分子の低温結晶化
- 1.2 高分子と水分子の分子運動性と低温結晶化
- 2.高分子に水和した水分子の動的構造と相互作用
- 2.1 中性子準弾性散乱による水分子の動的構造解析
- 2.2 含水PVPに水和した水分子の動的構造
- おわりに
4節 タンパク質のステンレス鋼表面に対する付着挙動
- はじめに
- 1.タンパク質のステンレス鋼表面への吸着挙動把握のための手法
- 1.1 ふき取り法
- 1.2 枯渇法
- 1.3 エリプソメトリー法
- 1.4 水晶振動子マイクロバランス法 (Quartz Crystal Microbalance; QCM)
- 1.5 高感度反射法
- 2.ステンレス鋼表面へのタンパク質吸着挙動
- 2.1 タンパク質の吸着に寄与する相互作用1)
- 2.2 タンパク質のステンレス鋼への付着量
- 2.3 タンパク質のステンレス鋼への吸着の不可逆性1)
- 2.4 タンパク質のステンレス鋼への吸着の速度論
- 2.5 タンパク質の吸着部位
- 3.タンパク質のステンレス鋼表面への付着の抑制の試み
- おわりに
5節 金属バイオマテリアル表面でのタンパク質吸着と細胞接着
- はじめに
- 1.金属表面とタンパク質吸着
- 1.1 金属表面の酸化物層
- 1.2 表面酸化物層とタンパク質・細胞の相互作用
- 2.タンパク質吸着のメカニズム
- 2.1 表面自由エネルギーとぬれ性
- 2.2 表面電荷
- 3.細胞接着のメカニズム
- 3.1 タンパク質の役割
- 3.2 細胞接着分子
- 3.3 細胞内情報伝達
- 4.表面改質とその効果
- 4.1 表面改質手法
- 4.2 表面改質がタンパク質吸着に与える影響
- 4.3 表面改質が細胞接着に与える影響
- おわりに
6節 接触角によるタンパク質吸着量の評価
- はじめに
- 1.ぬれ性と接触角
- 1.1 ぬれ性
- 1.2 表面と界面
- 1.3 親水性,疎水性,撥水性
- 1.4 ぬれ性と接触角
- 2.表面張力と表面自由エネルギー
- 2.1 表面張力と界面張力
- 2.2 表面自由エネルギーと界面自由エネルギー
- 2.3 表面張力の由来
- 2.4 表面自由エネルギーの成分分けと表面自由エネルギー解析
- 2.5 固体の表面張力,表面自由エネルギーの意味
- 3.接触角と表面張力・界面張力との関係
- 3.1 ぬれ性と分子間力
- 3.2 Youngの式
- 4.接触角測定と表面自由エネルギー解析
- 4.1 接触角測定
- 4.2 表面自由エネルギー解析
- 5.タンパク質吸着の評価事例
- 5.1 タンパク質の吸着量と接触角との関係
- 5.2 タンパク質の吸着量と表面自由エネルギーとの関係
- おわりに
7節 デバイスへの吸着抑制を目的とした界面活性剤の活用
- はじめに
- 1.デバイスへの吸着抑制における界面活性剤の役割
- 2.バイオ医薬品における界面活性剤の活用状況
- 2.1 ポリソルベート類
- 2.2 ポロキサマー類
8節 エピタキシャルグラフェン上へのタンパク質・アミノ酸吸着特性の電気的評価
- はじめに
- 1.実験手法
- 1.1 デバイス作製
- 1.2 吸着特性評価
- 2.吸着特性結果
- 2.1 タンパク質吸着特性
- 2.2 アミノ酸吸着特性
9節 バイオフィルムの付着性評価
- はじめに
- 1.バイオフィルムとは
- 2.バイオフィルムの生成法
- 2.1 実環境で実際に生成したバイオフィルムの利用
- 2.2 実験室環境下での単一菌バイオフィルム生成
- 2.3 実験室環境下での常在菌バイオフィルム生成
- 3.バイオフィルムの定量法
- 3.1 クリスタルバイオレット染色法
- 3.2 バイオフィルム中菌数の測定
- 3.3 その他の定量法
- 4.定量以外のバイオフィルムの付着性評価
- 5.さいごに
第4章 抗血栓性コーティング技術の開発と評価
1節 抗血栓コーティングの設計において有用な評価技術
- はじめに
- 1.抗血栓コーティングの設計思想
- 2.抗血栓性コーティングの設計において有用な評価技術
- 2.1 血小板粘着試験 シート
- 2.2 抗血栓性持続性評価 チューブ
- 2.3 In vitro血液循環評価 人工肺
- 2.4 In vitro血液循環評価 ステント
- 終わりに
2節 血液浄化膜に対する抗血栓性コーティングポリマAN-MPCの開発
- はじめに
- 1.敗血症に対する血液浄化膜の研究背景
- 2.透析膜およびhemofilter膜に対する抗血栓性の技術
- 2.1 透析膜に対する抗血栓性技術
- 2.2 敗血症に使用するhemofilter膜に対する抗血栓性技術
- 3.透析膜に対するMPCポリマ表面修飾の先行研究
- 4.新たに開発したhemofilter膜に対する抗血栓性AN-MPCポリマ
- 4.1 AN-MPCポリマ開発のコンセプト
- 4.2 AN-MPCポリマコーティング溶液の作成と機能評価
- 4.3 AN-MPCポリマの将来性と課題
3節 ポリエチレン (PE) の改質による抗血栓性化を可能にする新規バイオマテリアル
- はじめに
- 1.従来技術の現状と課題
- 2.側鎖結晶性ブロック共重合体によるPEの表面改質機能
- 3.SCCBCにより改質したPEの抗血栓性
- 4.他の難改質性高分子基材への展開性
- 5.ステンレスへの抗血栓性付与
4節 コラーゲンの立体構造修飾による脱細胞組織の抗血性化
- はじめに
- 1.脱細胞組織
- 1.1 脱細胞方法
- 1.2 脱細胞組織の構造と特性
- 2.化学修飾による抗血栓化
- 2.1 アンチファウリング特性をもつ合成高分子の固定化
- 2.2 生理活性分子の固定化
- 2.3 生理活性を有するペプチドの固定化
- 3.構造修飾による抗血栓性化
- 3.1 脱細胞組織の乾燥/エタノール処理
- 3.2 処理による脱細胞組織の構造変化
- 3.3 血液応答と組織再生
- 4.まとめ
5節 抗血栓性ポリマーの脱細胞化肝臓足場への活用
- はじめに
- 1.脱細胞化骨格を用いた臓器再生
- 1.1 肝臓の脱細胞化
- 1.2 肝臓の再細胞化
- 2.脱細胞化臓器の移植
- 2.1 心臓
- 2.2 肺
- 2.3 肝臓
- 2.4 小腸
- 2.4 腎臓
- 3.移植における課題
- 3.1 再細胞化
- 3.2 血栓抑制
- 3.2.1 抗血栓ポリマーコーティング
- まとめ
第5章 タンパク質の吸着促進をさせる表面処理技術と材料の開発
1節 細胞培養基材の設計ポイント
- はじめに
- 1.細胞を取り巻く培養環境
- 2.細胞および培養技術の分類
- 2.1 培養細胞の分類
- 2.2 培養方法の分類
- 3.培養基材と細胞の関係性
- 3.1 タンパク質の吸着現象
- 3.2 細胞の接着現象
- 4.培養基材の設計ポイント
2節 炭素系薄膜への細胞接着性タンパク質吸着性評価
- はじめに
- 1.生体適合性付与への炭素系薄膜の応用
- 1.1 生体適合性
- 1.2 表面処理技術
- 1.3 炭素系薄膜
- 2.X線光電子分光 (XPS) によるタンパク質吸着性評価
- 2.1 表面吸着タンパク質の評価
- 2.2 XPS法による表面吸着タンパク質の評価
- 3.ダイヤモンドライクカーボン (DLC) 薄膜へのタンパク質吸着
- 3.1 生体適合性
- 3.2 各種基板との比較
- 3.3 各種タンパク質の吸着
- おわりに
3節 タンパク質吸着のためのバイオセラミック粒子の表面機能化
- はじめに
- 1.生体骨におけるタンパク質の吸着現象
- 2.バイオセラミックス粒子と表面機能
- 2.1 水酸アパタイト粒子
- 2.2 非晶質シリカ粒子
- 3.バイオセラミック粒子に形成される表面層
- 3.1 体液における表面層の形成
- 3.2 表面層の水和状態とそのタンパク質吸着への影響
- 3.3 非アパタイト層の形成とタンパク質吸着能
- 3.4 新たな層形成を実現する非晶質シリカ粒子
- おわりに
4節 光照射による細胞の接着促進・忌避の制御
- はじめに
- 2. 動作原理と物質の選択
- 3. 細胞培養器の構造と光応答
- 4. TypeI細胞培養器における紫外光照射下での細胞接着挙動
- 5. TypeII細胞培養器における紫外光照射下での細胞接着挙動
- 6. 光の局所照射による細胞の接着領域制御
- おわりに
5節 細胞接着を光制御できる機能性基板
- はじめに
- 1.光応答基板の原理と作製
- 1.1 作動原理と光照射方法
- 1.2 光応答ガラス基板作製
- 2.光応答ガラス基板の応用
- 2.1 幾何学形状に応じた細胞集団移動
- 2.2 細胞外マトリクスの種類の変化に対する集団移動挙動
- 3.ガラス以外の材料の光機能化
- 3.1 金蒸着基板に基づくECM密度が制御された光応答基板
- 3.2 ハイドロゲルに基づく弾性率が制御された光応答基板
- 4.結論
6節 細胞を性質変換させる三次元培養技術に向けた細胞架橋素子の開発
- はじめに
- 1.WS-CODYの設計と合成およびその化学反応性
- 1.1 WS-CODYの開発
- 1.2 WS-CODYとアジド低分子との反応性解析
- 2. WS-CODYによる等電点選択的タンパク質修飾
- 3. WS-CODYを用いた三次元培養技術への応用
- 3-1. アジド修飾ヒアルロン酸を用いたダブルクリック架橋による細胞凝集体の作製
- 3-2. 長期培養による細胞凝集体の遺伝子変動
- おわりに
7節 セラックへの細胞接着性の付与
- 1.本研究の背景
- 2.セラックとは
- 3.細胞接着性を保持したセラックの開発
- 3.1 修飾セラックの化学合成
- 3.2 修飾セラックの化合物同定
- 3.3 修飾セラックの水に対する接触角測定
- 3.4 修飾セラックの細胞接着、増殖性の評価
- 3.5 光照射により細胞接着・増殖性を失うセラックの開発
- 4.まとめ
8節 ナノカーボン材料表面へのタンパク質の結合機構:アミノ酸レベルでの理解
- はじめに
- 1.グラフェンとカーボンナノチューブの構造
- 2.アミノ酸とナノカーボンの相互作用
- 2.1 実験的手法1:カーボンナノチューブへのアミノ酸の吸着量
- 2.2 実験的手法2:カーボンナノチューブ固定化カラムへのアミノ酸の保持力
- 2.3 計算科学的手法1:量子化学計算
- 2.4 計算科学的手法2:分子動力学計算
- 3.芳香族親和性 (アロマフィリシティ) による結合サイトの予測
- おわりに
9節 ソフト界面揺らぎの定量的評価とタンパク質吸着との相関関係
- はじめに
- 1.ソフト界面
- 1.1 ベシクル
- 1.2 支持膜
- 1.2.1 高分子支持膜
- 1.2.2 脂質膜
- 1.3 ソフト界面の揺らぎ構造
- 1.3.1 高分子支持膜
- 1.3.2 脂質膜 (ベシクルと平面膜)
- 2. ソフト界面へのタンパク質の吸着
- 2.1 水晶振動子法による吸着評価
- 2.1.1 高分子支持膜
- 2.1.2 脂質膜
- 2.2 カルセイン漏出挙動に基づく吸着評価
- 2.3 誘電分散解析による吸着測定
- 2.4 その他の方法
- 2.1 水晶振動子法による吸着評価
- 3. タンパク質の膜表界面への吸着現象
- 3.1 タンパク質分子の物性
- 3.2 吸着に関わるタンパク質の表面物性
- 3.3 タンパク質-脂質膜間相互作用に基づく吸着現象の解析
- 4. ソフト界面とタンパク質の吸着相関
第6章 医薬品包装/医療機器材料に関わる規制
1節 ISO 10993 医療機器の生物学的評価
- はじめに
- 1.ISO 10993シリーズと国内ガイダンス
- 2.生物学的安全性評価項目の種類
- 3.生物学的評価の体系的手引き
2節 日本薬局方 生物学的安全性評価
- はじめに
- 1.日本薬局方 参考情報
- 2.医薬品容器の品質管理としての生物学的安全性評価
3節 生物学的安全性試験の概要
- はじめに
- 1.細胞毒性試験
- 2.感作性試験
- 3.刺激性試験/皮内反応試験
- 4.発熱性物質試験
- 5.全身毒性試験
- 6.埋植試験
- 7.血液適合性試験
- 8.遺伝毒性試験
- 9.がん原性、生殖発生毒性、生分解性
- 10.物理学的・化学的情報
- 11.生物学的安全性試験における抽出条件
4節 E&L試験の実施ポイント
- 1.はじめに
- 2.ICH Q3Eガイドライン
- 3.具体的なガイダンス
- 4.対象となる医薬品とリスクファクター
- 5.各種プラスチックの製造の流れ
- 6.抽出物、浸出物の定義
- 7.抽出物、浸出物の評価の手順
- 8.PQRIによる抽出物、浸出物の評価手順
- 8.1 情報収集と有害物質の選出
- 8.2 抽出条件の検討、抽出物試験、リスト化
- 8.3 リスクアセスメント:安全性、毒性評価
- 8.4 浸出物試験:検出、同定、定量
- 9.抽出物、浸出物の分析
- 10.様々な機器分析とその抽出法
- 10.1 GC/MSの代表的なサンプル前処理法溶媒抽出法
- 10.2 LC/MS代表的なサンプル前処理法溶媒抽出法
- 10.3 GC/MSによる分析
- 10.4 LC/MSによる分析
- 10.5 プラスチック中の添加剤の保持時間をシミュレーションするソフトウェア
出版社
お支払い方法、返品の可否は、必ず注文前にご確認をお願いいたします。
体裁・ページ数
A4判 437ページ
ISBNコード
978-4-86798-040-8
発行年月
2024年9月
販売元
tech-seminar.jp
価格
80,000円 (税別) / 88,000円 (税込)
これから開催される関連セミナー
関連する出版物
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2012/7/4 | 薬事法・景品表示法 実践 戦略パック |
| 2012/3/24 | 高機能急性期病院にとっての2012年度診療報酬改定の影響と対策 |
| 2012/3/13 | 超入門 GMP基礎セミナー |
| 2012/3/5 | 育毛剤・発毛剤 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2012/2/16 | システムの適格性確認および回顧的バリデーションの具体的実施方法 |
| 2012/2/14 | LIMS導入に関する導入の留意点セミナー |
| 2012/2/9 | 厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理GL」対応のための「回顧的バリデーション」および「リスクアセスメント」実施方法 |
| 2012/1/20 | 24年度診療報酬改定におけるDPC評価の全貌 |
| 2011/12/22 | 光学活性医薬品開発とキラルプロセス化学技術 |
| 2011/12/14 | QCラボにおける厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理GL」対応セミナー |
| 2011/12/10 | 製薬大手5社 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2011/11/7 | eCTD申請 「-ここまで身近になったeCTD申請-」 |
| 2011/9/1 | 厚労省ER/ES指針対応実施の手引き |
| 2011/8/29 | グローバルスタンダード対応のためのCSV実施方法 |
| 2011/8/24 | 厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理GL」対応 "SOP作成"実践講座 |
| 2011/8/3 | 「回顧的バリデーション」および「リスクアセスメント」実施方法 |
| 2011/7/10 | 抗癌剤 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2011/7/5 | 分析機器やLIMSのバリデーションとER/ES指針 |
| 2011/7/1 | コンピュータバリデーション実施の手引き |
| 2011/6/30 | 医療機器 技術開発実態分析調査報告書 |