技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
核酸医薬・mRNA医薬の製造分析の基礎と基盤技術開発
核酸医薬・mRNA医薬の製造分析の基礎と基盤技術開発
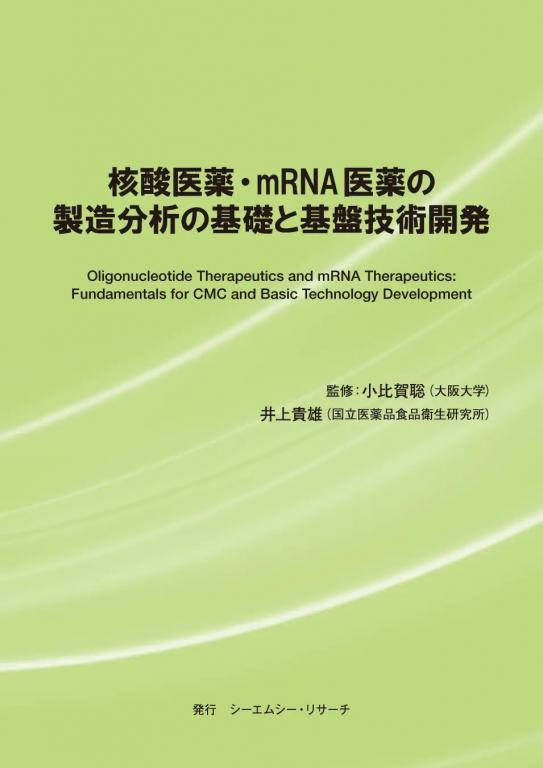
ご案内
核酸医薬は、核酸あるいは修飾核酸が十数〜数十塩基連結したオリゴ核酸で構成され、タンパク質に翻訳されることなく直接生体に作用するもので、化学合成により製造される医薬品であると言われている。2022年12月時点において、日米欧合わせて16品目の核酸医薬が承認されており、従来の低分子医薬や抗体医薬では治療が困難であった希少疾患や難治性疾患に対する新たな治療薬として確固たる地位を築きつつある。一言で核酸医薬といっても、そこには構造や作用機序が異なる様々な種類が存在する。例えば一本鎖核酸であるアンチセンス核酸は、疾病の原因となる遺伝子のmRNAやpre-mRNAに配列特異的に結合し薬効を発揮する。翻訳過程を阻害して疾病を引き起こすタンパク質の生成を阻害するのみならず、配列設計や化学修飾の仕方を調節することで、スプライシング過程を制御することも可能である。siRNAは二本鎖のRNAより構成されており、RISCと呼ばれるRNA-タンパク質複合体を介して標的となるmRNAを切断し翻訳過程を阻害する。また核酸アプタマーは、その立体構造により標的分子を厳密に認識するため、核酸で作られた抗体様分子ともいわれている。このように、核酸医薬の種類は多岐にわたるが、いずれも化学合成により製造されるという点は共通である。
一方、mRNA医薬はその名の通り、標的タンパク質の遺伝情報をコードしたmRNAを治療薬あるいは予防薬として用いるものである。薬効を示すのはmRNAそのものではなく、投与したmRNAから翻訳されるタンパク質であるという点が核酸医薬とは異なっている。また、核酸医薬はその鎖長が十数から数十塩基程度であり化学合成によって製造することが可能であるが、mRNAは数百塩基から数千塩基と鎖長が長く一般的には化学合成ではなく酵素反応を利用したinvitro転写系により合成される。mRNA医薬のうち、抗原タンパク質を発現させることでその抗原に対する免疫を誘導するものがmRNAワクチンである。新型コロナウイルス感染症に対するmRNAワクチンが驚異的なスピードで開発され全世界で利用されるようになったことで、mRNAワクチンを含むmRNA医薬に対する期待は大いに高まっている。感染症に対するmRNAワクチンの他にもがんやその他の難治性疾患に対するmRNA医薬に関する研究開発が世界中で進められており、約100品目もの候補品が臨床試験段階にある。
核酸医薬とmRNA医薬は、その作用メカニズムや鎖長、製造法などは異なるものの、用いられている技術には共通する点も多い。例えば、核酸医薬もmRNA医薬も生体内での安定性や細胞内への移行性が課題となる。そのため、いずれにおいても、適切な化学修飾や人工核酸技術、標的臓器や細胞へ移行させるためのデリバリー技術の利用が必要不可欠となっている。こうした核酸医薬及びmRNA医薬の実用化を支える共通の技術については、これまで長く研究されてきた核酸医薬やその基盤を築く核酸化学、DDS研究の成果を、mRNA医薬にも利用することが可能である。また、両者の分析法についても共通した考え方や技術が用いられている。
本書では、第1章から第3章では「核酸医薬」を、第4章から第6章では「mRNA医薬」を取り上げ、それぞれの領域の第一線で研究開発を牽引する産官学の先生方に執筆いただいた。「核酸医薬」、「mRNA医薬」ともに、概論を紹介したのちに、それぞれの製造法並びに分析法を詳細にまとめている。さらに、人工核酸技術や配列設計法、デリバリー手法などの基盤技術開発に関する最新の研究成果を幅広く紹介した。また、本書の最後には核酸医薬・mRNA医薬の市場概況や製造支援の状況についても触れている。本書が核酸医薬及びmRNA医薬の共通点と相違点、そして現在の技術開発動向を理解し、今後の研究の方向性を考える上で読者の皆様の一助になれば幸いである。
最後に、ご多忙のところ貴重な時間を割き執筆いただいた先生方に心より感謝申し上げたい。
2022年12月吉日
阪大学大学院 薬学研究科
小比賀 聡
目次
序論 核酸医薬とmRNA医薬
─RNAレベルでの生体制御─
井上貴雄
- 1 はじめに
- 2 核酸医薬とmRNA医薬の違い
- 3 核酸医薬の品質評価
- 4 mRNA医薬の品質評価
- 5 核酸医薬の規制整備
- 6 mRNA医薬の規制整備
- 7 おわりに
- 脚注、参考文献
第1章 核酸医薬概論 (核酸医薬とは)
第1節 核酸医薬概論
宮田完二郎
- 1 はじめに
- 2 核酸医薬の基本構造と作用機序
- 3 核酸医薬の体内動態とデリバリー技術
- 4 おわりに
- 参考文献
第2節 核酸医薬品のCMC概論
滝口直美
- 1 はじめに
- 2 オリゴヌクレオチドの製造
- 3 オリゴヌクレオチドの分析
- 3.1 特性
- 3.2 規格及び試験方法
- 3.3 オリゴヌクレオチドの不純物管理
- 4 オリゴヌクレオチドの製剤
- 5 核酸医薬品の品質に関する規制整備の現状
- 6 最後に
- 謝辞、参考文献
第2章 核酸医薬の製造と分析
第1節 オリゴ核酸の工業的生産と次世代の長鎖RNA生産
羽城周平、佐野坂真人、南海浩一
- 1 はじめに
- 2 オリゴ核酸の工業的生産
- 3 酵素ライゲーションによる長鎖RNAの作製
- 4 微生物による長鎖RNAの発酵生産
- 5 おわりに
- 参考文献
第2節 オリゴ核酸のバッチ式固相合成によるスケールアップ化
閨 正博
- 1 はじめに
- 2 オリゴヌクレオチドの固相合成
- 3 バッチ式固相合成法の弊社の取り組み
- 3.1 バッチ式合成機の開発
- 3.2 カラム充填式合成とバッチ式合成法との製品品質の比較
- 3.3 バッチ式固相合成法によるスケールアップ化
- 4 おわりに
- 参考文献
第3節 オリゴ核酸合成用担体NittoPhaseTM HLの開発とそれを用いたオリゴ核酸の大量合成
笠原 剛、岩本正史
- 1 はじめに
- 2 核酸合成能におけるNPHLとCPGの比較
- 3 NPHLを用いたオリゴ核酸の大量合成における製造パラメーターの最適化
- 3.1 固相担体の充填量
- 3.2 洗浄および各工程における固相担体の膨潤によるカラム内圧力の影響
- 3.3 脱保護工程
- 参考文献
第4節 MALDI-MSによるアンチセンス核酸の検出と構造解析
西風隆司
- 1 MALDI法とは
- 2 核酸測定に用いられるMALDIマトリックス
- 3 MALDI-TOF MSによるモデル核酸医薬品の検出
- 4 オリゴ核酸の配列確認法
- 5 MALDI-ISDの原理とオリゴ核酸イオンの開裂
- 6 MALDI-ISDによるモデル核酸医薬品の配列確認
- 7 まとめ
- 謝辞、参考文献
第5節 LC-MS/MSを用いたオリゴ核酸分析法の原理とその実例
唐澤 薫
- 1 はじめに
- 2 LC-MS/MS systemの概要および測定法
- 3 定性分析法および分析例
- 3.1 主成分の精密質量、同位体分布、配列の確認
- 3.1.1 精密質量、同位体分布の確認
- 3.1.2 配列確認
- 3.2 不純物・代謝物の検出、同定、構造推定
- 3.2.1 不純物・代謝物の検出、同定
- 3.2.2 不純物・代謝物の構造推定
- 3.1 主成分の精密質量、同位体分布、配列の確認
- 4 定量分析法および分析例
- 4.1 相対定量
- 4.2 絶対定量
- 5 Acoustic Ejection Mass Spectrometry (AEMS) を用いた高速分析
- 5.1 AEMSの概要および測定法
- 5.2 AEMSを用いた分析例 – 高速分析
- 6 おわりに
- 謝辞、参考文献
第6節 高分解能LC-MSによるオリゴ核酸の特性解析
高原健太郎
- 1 オリゴ核酸分析におけるLC-MSの有用性
- 2 IPRP-LC-MSにより明らかにできるオリゴ核酸の特性
- 2.1 Full MS測定によるFLPおよび不純物の検出・質量確認
- 2.2 MS/MS測定によるオリゴ核酸の配列解析
- 3 オリゴ核酸医薬品不純物の相対定量
- 4 まとめ
- 参考文献
第7節 オリゴ核酸の2D-LC/MSの概要と分析事例
瀬崎浩史
- 1 はじめに
- 2 2D-LCの概要と分離モード
- 2.1 2D-LCの概要
- 2.2 2D-LCを使用した分析モード
- 3 2D-LC/MSを使用したオリゴ核酸分析事例
- 4 まとめ
- 謝辞
第8節 イオンモビリティー分離の原理と核酸医薬品への応用
廣瀬賢治
- 1 はじめに:核酸医薬品の分離分析
- 2 イオンモビリティー分離
- 3 核酸医薬品のイオンモビリティー分離の応用例
- 4 おわりに
- 参考文献
第3章 核酸医薬の基盤技術開発
第1節 アンチジーン核酸医薬を志向した非天然型3本鎖DNA形成を可能とする人工核酸の開発
谷口陽祐
- 1 3本鎖DNA形成とアンチジーン核酸の作用メカニズム
- 2 3本鎖DNA形成の問題点と解決法
- 2.1 プリンリッチなTFOの性質
- 2.2 3本鎖DNA形成の本質的な制限
- 2.3 アンチパラレル型3本鎖DNA形成のための人工核酸
- 3 人工核酸 (シュードシチジン誘導体) の分子設計と機能評価
- 4 アンチジーン核酸としての機能検討
- 4.1 hTERT遺伝子を標的としたアンチジーン核酸の創成
- 4.2 アンチジーン核酸 (AGO) の核内利用率の向上戦略
- 5 まとめと今後の展望
- 参考文献
第2節 4′-チオ核酸によるセントラルドグマへの挑戦
田良島典子、南川典昭
- 1 はじめに
- 2 DNAを鋳型とした4′-チオDNAの複製
- 3 4′-チオDNAから4′-チオRNAへの転写
- 4 4′-チオRNAからタンパク質への翻訳
- 5 4′-チオDNA→4′-チオRNA→タンパク質の連続的遺伝子発現反応
- 6 おわりに
- 参考文献
第3節 オフターゲット効果を回避するsiRNA医薬の分子設計
小林芳明、程久美子
- 1 はじめに
- 2 siRNAによる遺伝子発現制御機構
- 2.1 siRNAによるRNA干渉のメカニズム
- 2.2 ヒトで有効なsiRNAの配列規則性の発見
- 3 siRNAによるオフターゲット効果とそれを回避する分子設計
- 3.1 siRNAによるオフターゲット効果のメカニズム
- 3.2 塩基対合力を制御してオフターゲット効果を回避する手法
- 3.3 化学修飾により塩基対合力を制御してオフターゲット効果を回避する手法
- 3.4 化学修飾により立体障害を誘導することでオフターゲット効果を回避する手法
- 4 おわりに
- 参考文献
第4節 核酸やドラッグデリバリーシステムに対する免疫活性化の基礎と応用
清水太郎、高田春風、石田竜弘
- 1 はじめに
- 2 ドラッグデリバリーシステムによる核酸の体内・細胞内動態制御
- 3 核酸やドラッグデリバリーシステムに対する自然免疫応答
- 3.1 パターン認識受容体
- 3.2 補体系
- 3.3 サイトカイン・ケモカイン
- 4 核酸やドラッグデリバリーシステムに対する獲得免疫応答
- 4.1 獲得免疫
- 4.2 核酸に対する抗体誘導
- 4.3 PEGに対する抗体誘導
- 5 核酸やドラッグデリバリーシステムに対する免疫応答の回避
- 5.1 化学修飾・物性制御
- 5.2 免疫抑制・免疫寛容誘導
- 6 おわりに
- 参考文献
第5節 エクソソーム改変技術によるドラッグデリバリーシステムの開発と核酸医薬品への応用
吉岡祐亮
- 1 はじめに
- 2 エクソソームとは
- 3 エクソソームの取り込み
- 4 エクソソームの体内動態
- 5 デリバリーのキャリアとしてのエクソソーム
- 6 組織特異的な送達を目指したエクソソームDDSの開発
- 7 エクソソームの臨床応用
- 8 おわりに
- 参考文献
第4章 mRNA医薬概論 (mRNA医薬とは)
第1節 mRNA医薬概論:mRNAをクスリとして用いる
位髙啓史
- 1 mRNA創薬:その開発経緯
- 2 mRNA創薬における3要素
- 2.1 mRNA
- 2.2 DDS
- 2.3 mRNAを用いて投与する「情報」
- 参考文献
第2節 mRNA医薬の製造概論
吉田哲郎
- 1 はじめに
- 2 mRNA原薬の製造
- 2.1 In vitro Transcription
- (1) 鋳型DNA
- (2) RNAポリメラーゼ
- (3) 基質NTP (ヌクレオシド三リン酸)
- 2.2 mRNA塩基配列
- (1) コドン最適化
- (2) UTR最適化
- (3) mRNA高次構造
- (4) 5′-Cap構造
- (5) Poly (A) 鎖
- 2.3 mRNA精製
- 2.1 In vitro Transcription
- 3 ドラッグデリバリーシステム (DDS)
- 3.1 mRNA内包脂質ナノ粒子 (LNP)
- 3.2 LNPの製造方法
- 4 次世代型mRNA医薬
- 4.1 自己増幅型RNA (saRNA)
- 4.2 環状RNA (CircRNA)
- 5 今後の課題
- 5.1 組織特異的mRNA発現技術
- 5.2 個別化がんワクチンへの応用
- 5.3 次に来るパンデミックへの対応
- 参考文献
第5章 mRNA医薬の製造と分析
第1節 mRNA医薬の製造:タカラバイオが提供するソリューション
榎 竜嗣
- 1 はじめに
- 2 mRNA製造プロセス
- 3 品質試験
- 4 タカラバイオのmRNA医薬製造に対するソリューションの提供
- 5 おわりに
- 参考文献
第2節 mRNA医薬の開発製造受託事業の立ち上げ
高木大輔
- 1 はじめに
- 2 再生医療や創薬研究におけるmRNA応用
- 3 日本でのmRNA製造拠点立ち上げとmRNAの設計、製造における課題と対応
- 3.1 日本でのmRNA医薬品製造レベルの拠点確保
- 3.2 mRNA医薬品向け製造における課題
- 3.3 mRNAの設計について
- 4 mRNA医薬品への期待
- 参考文献
第3節 mRNA医薬の製造・分析技術
中島和幸
- 1 はじめに
- 2 mRNAの構造と分子設計
- 3 mRNA原薬の製造と品質管理
- 4 CDMOとしての役割
- 参考文献
第4節 mRNA医薬の製剤化
辻畑茂朝
- 1 mRNA医薬の製剤設計
- 1.1 mRNAのDDS製剤
- 1.2 脂質ナノ粒子の設計
- 2 脂質ナノ粒子のプロセス設計
- 2.1 粒子形成プロセス
- 2.2 ダウンストリームプロセス
- 3 おわりに
- 参考文献
第5節 高分解能LC-MSによるmRNA配列解析
高原健太郎
- 1 mRNA配列解析の難しさ
- 2 LC-MSによる配列解析に適したmRNA消化
- 3 消化されたmRNA断片の同定と配列解析
- 4 LC-MSによるmRNA配列解析の拡張性
- 4.1 化学修飾の同定
- 4.2 RNA不純物または混在するRNAの同定
- 5 まとめ
- 参考文献
第6節 mRNA医薬の分析
寺崎真樹
- 1 mRNA医薬
- 2 5′キャップ構造の分析
- 3 ポリA配列の分析
- 4 まとめ
- 参考文献
第6章 mRNA医薬の基盤技術開発
第1節 mRNAを医薬品として用いるための基盤技術
横尾英知、内田智士
- 1 はじめに
- 2 mRNAの高機能化
- 2.1 mRNAの化学修飾
- 2.2 自己増幅RNA
- 2.3 環状RNA
- 3 mRNAデリバリー
- 3.1 mRNAデリバリーの障壁と送達キャリア
- 3.2 脂質ベクター
- 3.3 リポポリプレックス
- 3.4 ポリプレックス
- 3.5 ペプチドベクター
- 3.6 ハイブリッドデリバリー材料
- 3.7 エクソソーム
- 4 mRNAの治療応用
- 5 おわりに
- 参考文献
第2節 脂質ナノ粒子を基盤とするmRNA医薬の開発
秋田英万
- 1 はじめに
- 2 DDSの観点から見たmRNA創薬のメリット
- 3 mRNAを搭載したLNPを形成する脂質材料の設計
- 4 国産の脂質様材料としてのssPalmの開発
- 5 ApoEを介した標的化・臓器標的化
- 6 今後の展望
- 6.1 LNPが引き起こす免疫応答制御
- 6.2 Extra-hepatic targeting
- 7 おわりに
- 参考文献
第3節 mRNA医薬品のドラッグデリバリーを可能にする化学修飾技術の開発と製剤化
大庭 誠
- 1 はじめに
- 2 mRNA医薬品の基礎
- 2.1 mRNA医薬品と遺伝子治療・バイオ医薬品との比較
- 2.2 mRNA医薬品の課題
- 3 化学修飾技術
- 3.1 Cap化技術
- 3.2 塩基の化学修飾
- 3.3 Poly (A) 付加
- 3.4 非翻訳領域最適化
- 3.5 コドン最適化
- 4 DDS技術
- 4.1 脂質ナノ粒子
- 4.2 合成高分子ナノ粒子
- 4.3 その他のDDS技術
- 5 おわりに
- 参考文献
第4節 mRNA医薬の技術動向
飯笹 久
- 1 mRNAとは何か
- 2 ワクチンの歴史
- 3 ワクチンとは何か
- 4 mRNAワクチンの原理
- 5 mRNAワクチン開発の歴史
- 6 mRNAワクチンとCap構造
- 7 新型コロナウイルスの流行とmRNAワクチン
- 8 新型コロナウイルスの変異株とmRNAワクチン
- 9 mRNAワクチンからmRNA医薬品への展開
- 10 まとめ
- 参考文献
第5節 翻訳効率最大化のためのmRNA分子設計
乙竹真美、平岡陽花、阿部 洋
- 1 はじめに
- 2 終止コドンを除いた環状mRNAの翻訳活性と生体内安定性の向上
- 3 位置特異的なホスホロチオエート修飾の導入による翻訳活性向上
- 4 化学的キャップ化反応を用いたmRNAの完全化学合成
- 5 最後に
- 参考文献
第7章 核酸医薬・mRNA医薬の市場動向
第1節 核酸医薬・mRNA医薬の市場トレンド
立花浩司
- 核酸医薬
- mRNA医薬
第2節 核酸医薬・mRNA医薬における製造支援サービス
立花浩司
- 1 概要
- 2 主要各社の動向と今後の展望
- 2.1 日東電工
- 2.2 エリクサジェン・サイエンティフィック・ジャパン (Elixirgen Scientific Japan)
- 2.3 アジレントテクノロジー (Agilent Technologies)
- 2.4 味の素バイオファーマサービス (ジーンデザイン)
- 2.5 日本触媒
- 2.6 住友化学
- 2.7 カネカユーロジェンテック (Kaneka Eurogentec S.A.)
- 2.8 東洋紡
- 2.9 神戸天然物化学
- 2.10 長瀬産業
- 2.11 十全化学
- 2.12 住商ファーマインターナショナル
- 2.13 ヤマサ醤油
- 2.14 アルカリス (ARCALIS)
- 2.15 主な市場参入企業の動向
- (1) イーザアールエヌーエー・イムノセラピーズ (Etherna Immunotherapies)
- (2) セロニック (Celonic AG)
- (3) コーデンファーマ (Corden Pharma GmbH)
- (4) ロンザ (Lonza Group AG)
- (5) メルクライフサイエンス (Merck Life Science)
- (6) サムスンバイオロジクス (Samsung Biologics)
- (7) レンチュラー・バイオファーマ (Rentschler Biopharma)
- (8) ラボラトリ・ファーマシューティカル・ロビ (Laboratorios Farmacéuticos Rovi)
- (9) サーモフィッシャーサイエンティフィック (Thermo Fisher Scientific)
- (10) ザルトリウス (Sartorius)
- (11) ベリタスインシリコ (Veritas In Silico)
- (12) AGCバイオロジクス
- (13) タカラバイオ
- (14) ステミルナ・セラピューティクス (Stemirna Therapeutics)
- 参考文献
出版社
体裁・ページ数
ISBNコード
発行年月
販売元
価格
案内割引について
シーエムシーリサーチからの案内をご希望の方は、割引特典を受けられます。
- Eメール案内を希望する方 :
- 冊子版: 81,000円(税別) / 89,100円(10%税込)
- 冊子版 + PDF版 (CD) セット: 90,000円(税別) / 99,000円(10%税込)
- Eメール案内を希望しない方 :
- 冊子版: 90,000円(税別) / 99,000円(10%税込)
- 冊子版 + PDF版 (CD) セット: 100,000円(税別) / 110,000円(10%税込)
これから開催される関連セミナー
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 海外販売も見据えた薬価算定ルール・薬価妥当性判断と当局交渉/戦略立案/シナリオ策定のポイント | オンライン | |
| 2025/12/19 | バイオ医薬品の薬物動態学 | オンライン | |
| 2025/12/19 | バイオ医薬品用原薬製造工場の施設・設備設計のポイント | オンライン | |
| 2025/12/19 | 新規モダリティにおける事業性評価手法 | オンライン | |
| 2025/12/22 | バイオ医薬品用原薬製造工場の施設・設備設計のポイント | オンライン | |
| 2026/1/6 | 新規モダリティにおける事業性評価手法 | オンライン | |
| 2026/1/13 | 海外販売も見据えた薬価算定ルール・薬価妥当性判断と当局交渉/戦略立案/シナリオ策定のポイント | オンライン | |
| 2026/1/22 | 医薬品・バイオ医薬品における事業開発の進め方と注意点 | オンライン | |
| 2026/1/23 | 医薬品・バイオ医薬品における事業開発の進め方と注意点 | オンライン | |
| 2026/1/23 | バイオ医薬品 (生物製剤) の開発・審査の現状と品質審査の視点 | オンライン | |
| 2026/1/23 | 核酸・mRNA医薬品の基礎および動態評価と送達技術の要点 | オンライン | |
| 2026/1/26 | バイオ医薬品 (生物製剤) の開発・審査の現状と品質審査の視点 | オンライン | |
| 2026/1/26 | 核酸・mRNA医薬品の基礎および動態評価と送達技術の要点 | オンライン | |
| 2026/1/29 | オルガノイドを活用したin vitro薬効・毒性・薬物動態評価 | オンライン | |
| 2026/1/29 | バイオ医薬品の品質・安定性向上を目指すタンパク質の凝集体分析と安定化戦略 | オンライン | |
| 2026/1/30 | 最近の裁判例の論点をふまえた核酸医薬品の特許戦略 | オンライン | |
| 2026/1/30 | GCTP省令に対応した再生医療等製品の製造品質管理とCPF設備運用の留意点 | オンライン | |
| 2026/2/3 | グローバル販売を見据えた薬価算定ルール・薬価妥当性判断と当局交渉のポイント | オンライン | |
| 2026/2/13 | オルガノイドを活用したin vitro薬効・毒性・薬物動態評価 | オンライン | |
| 2026/2/13 | 最近の裁判例の論点をふまえた核酸医薬品の特許戦略 | オンライン |
関連する出版物
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2025/1/27 | 世界の中分子医薬・抗体医薬、およびCDMO最新業界レポート |
| 2024/1/31 | 不純物の分析法と化学物質の取り扱い |
| 2023/2/28 | mRNAの制御機構の解明と治療薬・ワクチンへの活用 |
| 2022/11/30 | 抗体医薬品製造 |
| 2022/10/26 | バイオ医薬品の製剤安定化/高品質化のための不純物の規格設定と評価・管理手法 (製本版 + ebook版) |
| 2022/10/26 | バイオ医薬品の製剤安定化/高品質化のための不純物の規格設定と評価・管理手法 |
| 2022/9/29 | 核酸医薬品のCMC管理戦略 (製本版 + ebook版) |
| 2022/9/29 | 核酸医薬品のCMC管理戦略 |
| 2021/10/11 | 抗ウイルス薬 |
| 2021/10/11 | 抗ウイルス薬 (CD-ROM版) |
| 2021/8/31 | 創薬研究者・アカデミア研究者が知っておくべき最新の免疫学とその応用技術 |
| 2020/12/24 | バイオ医薬品 (抗体医薬品) CTD-CMC記載の要点 |
| 2019/5/31 | 医薬品モダリティの特許戦略と技術開発動向 |
| 2018/4/25 | 統計学的アプローチを活用した分析法バリデーションの評価及び妥当性 |
| 2018/1/30 | バイオ医薬品のCTD-Q作成 - 妥当性の根拠とまとめ方 - |